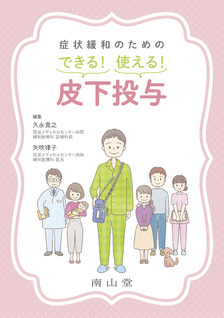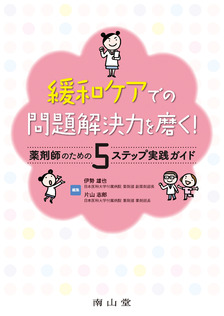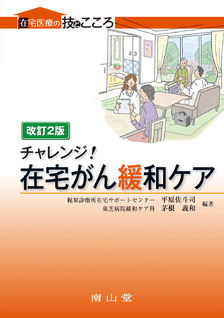カテゴリー: 癌・腫瘍学 | 総合診療医学/プライマリ・ケア医学
症状緩和のための
できる!使える! 皮下投与
1版
筑波メディカルセンター病院 緩和医療科 診療科長 久永貴之 編
筑波メディカルセンター病院 緩和医療科 医長 矢吹律子 編
定価
3,300円(本体 3,000円 +税10%)
- A5判 172頁
- 2020年8月 発行
- ISBN 978-4-525-42191-5
ありそうでなかった薬剤の皮下投与の教科書!
薬剤の皮下投与がこの一冊でまるごとわかる!
終末期患者の補液・投薬手段として重用されている薬剤の皮下投与方法は比較的低侵襲であるが,ほとんどの薬剤において添付文書範囲外の投与方法となり,有害事象や配合変化などへの対応・配慮も必要となる.本書では,終末期患者の症状緩和において皮下投与をより安全に,より有効に活用するための知見を整理して紹介する.
- 序文
- 本書ご利用にあたって
- 目次
- 書評 1
- 書評 2
- 書評3
序文
薬剤や輸液の皮下投与は緩和ケア病棟や在宅の現場では古くから広く行われてきた方法である.緩和ケアの先駆者たちが,静脈ルートが確保できない中で,できる限り患者の負担や侵襲を軽減するために紡ぎあげてきた知恵の結集ともいうべきものである.
一方で,その根拠は乏しく,成書等での記載もごく僅かであり,秘伝のワザとして引き継がれてきた面がある.本書は著者らの経験と現時点で得られる限りの根拠に基づき,秘伝のワザを広く利用していただけるように企画した.
筆者らの施設においては,緩和ケア病棟が開棟された20年ほど前より,できるものは皮下投与を検討する文化があった.そのため,皮下投与が広く普及している英国の成書を参考に,試行錯誤しながら皮膚障害や効果を見極めて,様々な薬剤を皮下投与してきた.その中で感じてきたのは,思っているよりも皮下投与できる薬剤は多く,思っているよりも効果があるということであった.
十分な配慮を行えば,皮下投与は患者負担が少なく緩和ケアの領域で非常に有用な投与方法である.本書を多くのがん患者の症状緩和に役立てていただけることを期待したい.
2020年6月
編者を代表して
久永貴之
一方で,その根拠は乏しく,成書等での記載もごく僅かであり,秘伝のワザとして引き継がれてきた面がある.本書は著者らの経験と現時点で得られる限りの根拠に基づき,秘伝のワザを広く利用していただけるように企画した.
筆者らの施設においては,緩和ケア病棟が開棟された20年ほど前より,できるものは皮下投与を検討する文化があった.そのため,皮下投与が広く普及している英国の成書を参考に,試行錯誤しながら皮膚障害や効果を見極めて,様々な薬剤を皮下投与してきた.その中で感じてきたのは,思っているよりも皮下投与できる薬剤は多く,思っているよりも効果があるということであった.
十分な配慮を行えば,皮下投与は患者負担が少なく緩和ケアの領域で非常に有用な投与方法である.本書を多くのがん患者の症状緩和に役立てていただけることを期待したい.
2020年6月
編者を代表して
久永貴之
本書ご利用にあたって
適応外使用についての注意
本書では,がん患者の症状緩和のために皮下投与が行われている薬剤について,添付文書上は皮下投与の適用がない医薬品についても,海外での文献や成書等での使用例,あるいは国内での臨床経験に基づき,紹介することとした.
しかしながら,その多くは適応外使用であり,皮下投与における有効性や安全性などが確認されていない.有効性については主に吸収等の問題から効果が充分に発現しない可能性があり,また安全性については,特に皮膚の刺激性について個別に必ず確認が必要である.さらに吸収が経静脈投与や筋肉内注射と比較すると遅れることがあるため,薬剤によっては過鎮静や呼吸抑制等の有害事象についても遅れて発現する可能性がある.そのため投与開始後には十分な状態の観察が望まれる.なお,本書では適応外使用であることをその都度表示はしていない.保険適用の有無については12頁の表1-3を参照していただきたい.
実際に投与を行う際には,患者・家族への説明と同意を得たうえで,全身状態等を含め個別に医療チームで十分に検討を行っていただきたい.
本書では,がん患者の症状緩和のために皮下投与が行われている薬剤について,添付文書上は皮下投与の適用がない医薬品についても,海外での文献や成書等での使用例,あるいは国内での臨床経験に基づき,紹介することとした.
しかしながら,その多くは適応外使用であり,皮下投与における有効性や安全性などが確認されていない.有効性については主に吸収等の問題から効果が充分に発現しない可能性があり,また安全性については,特に皮膚の刺激性について個別に必ず確認が必要である.さらに吸収が経静脈投与や筋肉内注射と比較すると遅れることがあるため,薬剤によっては過鎮静や呼吸抑制等の有害事象についても遅れて発現する可能性がある.そのため投与開始後には十分な状態の観察が望まれる.なお,本書では適応外使用であることをその都度表示はしていない.保険適用の有無については12頁の表1-3を参照していただきたい.
実際に投与を行う際には,患者・家族への説明と同意を得たうえで,全身状態等を含め個別に医療チームで十分に検討を行っていただきたい.
目次
1章 薬剤の皮下投与の目的と意義、投与方法の種類
A.皮下投与の種類
B.皮下投与の利点と欠点
C.皮下投与の実際
①持続皮下注射
②皮下輸液
③薬剤投与のための皮下点滴
D.皮下投与できる輸液剤・注射剤
2章 使用できる薬剤
1.皮下投与できる薬剤とは ―基礎的な視点から―
A.皮膚組織の構造と機能
B.製剤の物理学的な性質から推測する薬剤の皮膚刺激性
2.使用できる薬剤・気をつけるべき薬剤
A.維持輸液
B.鎮痛薬
C.向精神薬
D.抗菌薬
E.その他
3章 利用可能なポンプ
A.電動式精密型ポンプ
B.ディスポーザブルポンプ
4章 薬剤の組み合わせ、配合変化
A.配合変化とは
B.配合変化の要因
C.配合可否の判断基準
D.配合変化を予測する方法、回避する方法
E.臨床での活用F.活用の具体例
・緩和ケア領域で使用されると予想される薬剤の配合変化の表
5章 投与の注意点と対応方法
A.持続皮下注射
B.皮下輸液/薬剤の皮下点滴
6章 症例に基づいた皮下投与の実際
1.緩和ケア病棟 ―緩和ケア医の視点から―
A.悪性消化管閉塞
B.出血
C.悪心・嘔吐(+せん妄)
D.不眠
E.せん妄
F.治療抵抗性の苦痛に対する鎮静
2.一般病棟 ―看護師の視点から―
A.投与経路変更に関する事前の情報提供
B.使い慣れていない医療用麻薬を使用するときの注意点
3.在宅 ―在宅委の視点から―
A.在宅における薬剤皮下投与の準備と注意点
B.在宅でのポンプの準備とコストの算定
C.PCAの指導と注意点
D.注射剤の混合
E.今後の展望
持続皮下注射指示一覧
オピオイド換算表
索 引
A.皮下投与の種類
B.皮下投与の利点と欠点
C.皮下投与の実際
①持続皮下注射
②皮下輸液
③薬剤投与のための皮下点滴
D.皮下投与できる輸液剤・注射剤
2章 使用できる薬剤
1.皮下投与できる薬剤とは ―基礎的な視点から―
A.皮膚組織の構造と機能
B.製剤の物理学的な性質から推測する薬剤の皮膚刺激性
2.使用できる薬剤・気をつけるべき薬剤
A.維持輸液
B.鎮痛薬
C.向精神薬
D.抗菌薬
E.その他
3章 利用可能なポンプ
A.電動式精密型ポンプ
B.ディスポーザブルポンプ
4章 薬剤の組み合わせ、配合変化
A.配合変化とは
B.配合変化の要因
C.配合可否の判断基準
D.配合変化を予測する方法、回避する方法
E.臨床での活用F.活用の具体例
・緩和ケア領域で使用されると予想される薬剤の配合変化の表
5章 投与の注意点と対応方法
A.持続皮下注射
B.皮下輸液/薬剤の皮下点滴
6章 症例に基づいた皮下投与の実際
1.緩和ケア病棟 ―緩和ケア医の視点から―
A.悪性消化管閉塞
B.出血
C.悪心・嘔吐(+せん妄)
D.不眠
E.せん妄
F.治療抵抗性の苦痛に対する鎮静
2.一般病棟 ―看護師の視点から―
A.投与経路変更に関する事前の情報提供
B.使い慣れていない医療用麻薬を使用するときの注意点
3.在宅 ―在宅委の視点から―
A.在宅における薬剤皮下投与の準備と注意点
B.在宅でのポンプの準備とコストの算定
C.PCAの指導と注意点
D.注射剤の混合
E.今後の展望
持続皮下注射指示一覧
オピオイド換算表
索 引
書評 1
志真泰夫(日本ホスピス緩和ケア協会 理事長/筑波メディカルセンター 代表理事)
本書は、本邦初の皮下投与(薬剤の持続皮下注射、皮下輸液、薬剤投与のための皮下点滴)に関する知識とノウハウをまとめた専門書(monograph)である。ホスピス発祥の地であるイギリスでは、すでにこの種の専門書が出版されており、わが国でも皮下投与に関する専門書の出版が待たれていた。
皮下投与は、多くの緩和ケア病棟で日常的な手技となりつつあるが、その臨床的な根拠(evidence)や手技の標準化については未だ十分明らかにされているとは言えない状況であった。しかし、本書が出版されたことにより臨床的根拠が整理されて明確となり、手技についても一定の標準化が可能となった。特に皮下輸液と薬剤投与のための皮下点滴について、最新の知見が示されたことはプライマリケアに携わる実地医家にとって、有用であろう。
近年、在宅専門診療所の制度化をはじめプライマリケアにおける在宅ケアの重要性が増しているが、主に外来診療に携わってきた実地医家にとっては24時間・365日対応と訪問診療における臨床的ノウハウの習得は、在宅ケア参入の障壁となっている。その意味では緩和ケアで培われてきた皮下投与のノウハウは、これからの在宅ケアにおける診療の大きな助けとなるに違いない。
一方、解決しなければならない課題も多い。本書の冒頭に「適応外使用についての注意」が述べられている。本書では「添付文書上は皮下投与の適用がない医薬品」についても取り上げられており、有用性と安全性については十分な注意を要する。さらに、在宅ケアで使用する場合は、保険診療上使用できる医薬品が限られており、これについても十分な注意を要する。現時点では、患者と家族に十分な説明を行って同意を得て、診療録に記載し、さらに保険請求時に症状詳記を添付する手間ひまを惜しんではならない。今後、編者をはじめ緩和ケアやプライマリケアに携わる医師や薬剤師の努力でこれらの課題が解決に向かうことを切に願っている。
本書は、本邦初の皮下投与(薬剤の持続皮下注射、皮下輸液、薬剤投与のための皮下点滴)に関する知識とノウハウをまとめた専門書(monograph)である。ホスピス発祥の地であるイギリスでは、すでにこの種の専門書が出版されており、わが国でも皮下投与に関する専門書の出版が待たれていた。
皮下投与は、多くの緩和ケア病棟で日常的な手技となりつつあるが、その臨床的な根拠(evidence)や手技の標準化については未だ十分明らかにされているとは言えない状況であった。しかし、本書が出版されたことにより臨床的根拠が整理されて明確となり、手技についても一定の標準化が可能となった。特に皮下輸液と薬剤投与のための皮下点滴について、最新の知見が示されたことはプライマリケアに携わる実地医家にとって、有用であろう。
近年、在宅専門診療所の制度化をはじめプライマリケアにおける在宅ケアの重要性が増しているが、主に外来診療に携わってきた実地医家にとっては24時間・365日対応と訪問診療における臨床的ノウハウの習得は、在宅ケア参入の障壁となっている。その意味では緩和ケアで培われてきた皮下投与のノウハウは、これからの在宅ケアにおける診療の大きな助けとなるに違いない。
一方、解決しなければならない課題も多い。本書の冒頭に「適応外使用についての注意」が述べられている。本書では「添付文書上は皮下投与の適用がない医薬品」についても取り上げられており、有用性と安全性については十分な注意を要する。さらに、在宅ケアで使用する場合は、保険診療上使用できる医薬品が限られており、これについても十分な注意を要する。現時点では、患者と家族に十分な説明を行って同意を得て、診療録に記載し、さらに保険請求時に症状詳記を添付する手間ひまを惜しんではならない。今後、編者をはじめ緩和ケアやプライマリケアに携わる医師や薬剤師の努力でこれらの課題が解決に向かうことを切に願っている。
書評 2
木澤義之(神戸大学大学院医学研究科 先端緩和医療学)
編者の2人,久永貴之先生と矢吹律子先生は出身大学の後輩にあたり,学生時代からよく存じ上げており,しかも先生方が勤務している筑波メディカルセンター病院の緩和ケア病棟は私の緩和ケア医としての原点であることから,このような良書ができたことをとても誇らしく感じています.また,書評を書く機会をいただきましたことを心より感謝しています(なんか,こう明らかに自分が作った本ができた時より100倍くらい嬉しいです).
本書は,現在緩和ケアにおける薬剤の皮下投与に関する,唯一,最良の書であると断言できます.また,緩和ケアにおいて食事や水分を経口摂取できなくなった時に,どのように薬剤投与するかを20年間考え続けた執筆者の臨床知を集めた本だと思います.もちろん,臨床研究の結果や,基礎データなども網羅されていすが,最終的には,『今まで研究論文はないけれど,pHや浸透圧は投与に問題はなく,「筆者らの施設で使って大きな問題は生じていない」,「筆者らの後ろ向き試験で,副作用発生率は○○%である」』,と言う言葉に圧倒されます.現場で困ったときに見ることができたら,きっと「おーーっそうなんだ.じゃあ患者さんやご家族にしっかり説明して使ってみようか…」と考えるのではないかと思います.そう思わせる現場感がこの本には溢れていると感じています.加えて,配合変化,ポンプの種類と管理方法,合併症とその対処など臨床に不可欠な情報が過不足なく書かれており,まさに『緩和ケア専門家がリファレンスとして使える本』になっていると思います.ホスピス・緩和ケア病棟,緩和ケアチーム,在宅診療,訪問看護ステーションに勤務されている方には,皆さんの診療・ケアの傍らにおいていただきたいと感じました.ご一読をおすすめいたします!
編者の2人,久永貴之先生と矢吹律子先生は出身大学の後輩にあたり,学生時代からよく存じ上げており,しかも先生方が勤務している筑波メディカルセンター病院の緩和ケア病棟は私の緩和ケア医としての原点であることから,このような良書ができたことをとても誇らしく感じています.また,書評を書く機会をいただきましたことを心より感謝しています(なんか,こう明らかに自分が作った本ができた時より100倍くらい嬉しいです).
本書は,現在緩和ケアにおける薬剤の皮下投与に関する,唯一,最良の書であると断言できます.また,緩和ケアにおいて食事や水分を経口摂取できなくなった時に,どのように薬剤投与するかを20年間考え続けた執筆者の臨床知を集めた本だと思います.もちろん,臨床研究の結果や,基礎データなども網羅されていすが,最終的には,『今まで研究論文はないけれど,pHや浸透圧は投与に問題はなく,「筆者らの施設で使って大きな問題は生じていない」,「筆者らの後ろ向き試験で,副作用発生率は○○%である」』,と言う言葉に圧倒されます.現場で困ったときに見ることができたら,きっと「おーーっそうなんだ.じゃあ患者さんやご家族にしっかり説明して使ってみようか…」と考えるのではないかと思います.そう思わせる現場感がこの本には溢れていると感じています.加えて,配合変化,ポンプの種類と管理方法,合併症とその対処など臨床に不可欠な情報が過不足なく書かれており,まさに『緩和ケア専門家がリファレンスとして使える本』になっていると思います.ホスピス・緩和ケア病棟,緩和ケアチーム,在宅診療,訪問看護ステーションに勤務されている方には,皆さんの診療・ケアの傍らにおいていただきたいと感じました.ご一読をおすすめいたします!
書評3
緩和ケアや在宅ケアでの皮下投与を“科学”しよう!
田上恵太(東北大学大学院緩和医療学分野 講師)
緩和ケア関係者のSNSで大きな話題になっている本書をご存知でしょうか.これまでEBM(患者の意向,医療者の経験や技術,エビデンス)に基づいて纏められた教科書はありません.わが国初の緩和ケア・在宅ケア領域に親和性の高い各薬剤の皮下投与に関する専門書となる本書では,何となく行われてきた皮下投与を,薬学的な知見やエビデンスを基に薬剤毎に検証しています.「この輸液はpHと浸透圧の観点から…」「この薬剤の添加物は…」と物理的な特性を基に妥当性を突き詰めると共に,これまでの研究や症例報告,そして数多くの現場での経験を基に論理を展開しています.
輸液や鎮痛薬は勿論,抗生物質や抗てんかん薬など在宅緩和ケアで投与される薬剤,細かい配合変化や投与ルート・ポンプまで過不足なく網羅しています.「何となく」行っていた皮下投与が「根拠をもって安心して届けられる」ようになることは間違いありません! 明日のあなたを変える一冊,在宅医療,療養病床,緩和ケア病棟,福祉施設の医療従事者は必読です!
田上恵太(東北大学大学院緩和医療学分野 講師)
緩和ケア関係者のSNSで大きな話題になっている本書をご存知でしょうか.これまでEBM(患者の意向,医療者の経験や技術,エビデンス)に基づいて纏められた教科書はありません.わが国初の緩和ケア・在宅ケア領域に親和性の高い各薬剤の皮下投与に関する専門書となる本書では,何となく行われてきた皮下投与を,薬学的な知見やエビデンスを基に薬剤毎に検証しています.「この輸液はpHと浸透圧の観点から…」「この薬剤の添加物は…」と物理的な特性を基に妥当性を突き詰めると共に,これまでの研究や症例報告,そして数多くの現場での経験を基に論理を展開しています.
輸液や鎮痛薬は勿論,抗生物質や抗てんかん薬など在宅緩和ケアで投与される薬剤,細かい配合変化や投与ルート・ポンプまで過不足なく網羅しています.「何となく」行っていた皮下投与が「根拠をもって安心して届けられる」ようになることは間違いありません! 明日のあなたを変える一冊,在宅医療,療養病床,緩和ケア病棟,福祉施設の医療従事者は必読です!