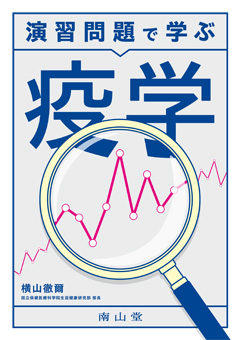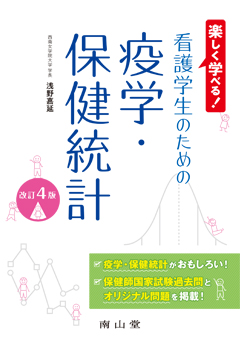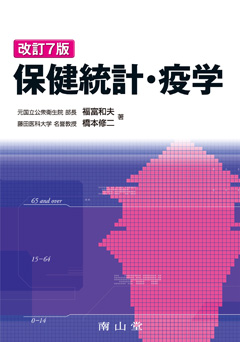カテゴリー: 衛生・公衆衛生学
演習問題で学ぶ 疫学
1版
国立保健医療科学院生涯健康研究部 部長 横山徹爾 著
定価
2,420円(本体 2,200円 +税10%)
- A5判 184頁
- 2024年8月 発行
- ISBN 978-4-525-18531-2
数字から読み解く医学!「疫学」をもっと身近に,もっとわかりやすく
演習問題を解きながら進む!巻末のまとめ問題で振り返り学習にも役立つ.
身近な問題や,よく見聞きするテーマを題材に演習問題を通じて疫学の原理が自然に身につく構成となっています.難しいと敬遠されがちな疫学を,初学者が理解しやすいよう基本事項に重点を置いて解説.最新の疫学データを用いた「演習」,章末の「確認問題」や巻末の「まとめ問題」は,医師,保健師の国家試験問題の出題基準にも準拠した内容となっています.
- 序文
- 目次
序文
「その“証拠”は何だろうか?」… 私は,講義で最初に問いかけることにしている.
たとえば,次のような誰でも知っている一般常識.
1.たばこを吸うと肺がんになりやすい
2.血中コレステロールが高いと心筋梗塞を起こしやすい
3.血圧が高いと脳卒中を起こしやすい
これらは,今日では医学研究者のみならず,多くの一般の人々が知っている医学常識である.しかし,何を根拠として言われるようになったのだろうか?と問いかけると,多くの場合,「たばこの煙には発がん物質が含まれているから」とか,「血圧や血清LDL コレステロールが高いと動脈硬化を起こしやすいから」などの答えが返ってくる.もちろん,これはメカニズムを説明するうえでは間違っていないが,この説明では「だから肺がんや脳卒中,心筋梗塞になりやすい“はずだ”」と言っているに過ぎないのであって,「本当に人間集団の中でそういう現象が起きているのか?」という問には答えていない.「人間集団の中でそういう現象が“本当に起きている”」ということを明快に示すことができるのが,「疫学研究」なのである.
このように,問いかけられた疑問に対して一度自分自身で考えてから説明を受けると理解が深まり,さらに類似の問題を解くことによって知識が定着していくと考えられる.そこで本書では,各章の最初に簡単な解説を行った後,「演習」で問題を解いたうえで解説を読んで理解し,各章末の「確認問題」で知識を定着するという構成になっている.疫学は公衆衛生学の基礎科学であり,人を対象とした医学研究の方法論として広く用いられている.学生の皆さんにとっては国家試験のための勉強はもちろんのこと,卒業研究や修士・博士課程で量的研究に取り組む際に必要となる学問である.また自治体や研究機関などで調査統計に関わる方々にとっては,その調査結果を正しく解釈し活用するために疫学の考え方は必須である.ぜひ本書の学習方法により疫学の考え方を身につけ,実践に活かす一助としていただければ幸甚である.
本書は「疫学入門演習」(東京医科歯科大学名誉教授 田中平三先生著)の内容を踏襲し,その改訂版としての位置づけでもある.疫学入門演習は私が大学生の頃から田中先生のご指導のもとで疫学を学んだ際のバイブル的な書であり,その隅々まで読み込んだことが,今の私の礎となっている.今回,その後継となる「演習問題で学ぶ疫学」の執筆を私にお任せくださったことは望外の喜びであり,田中先生には深甚なる謝意を捧げるとともに,今後のご健勝をお祈り申し上げたい.
2024 年7 月
国立保健医療科学院生涯健康研究部 部長
横山徹爾
たとえば,次のような誰でも知っている一般常識.
1.たばこを吸うと肺がんになりやすい
2.血中コレステロールが高いと心筋梗塞を起こしやすい
3.血圧が高いと脳卒中を起こしやすい
これらは,今日では医学研究者のみならず,多くの一般の人々が知っている医学常識である.しかし,何を根拠として言われるようになったのだろうか?と問いかけると,多くの場合,「たばこの煙には発がん物質が含まれているから」とか,「血圧や血清LDL コレステロールが高いと動脈硬化を起こしやすいから」などの答えが返ってくる.もちろん,これはメカニズムを説明するうえでは間違っていないが,この説明では「だから肺がんや脳卒中,心筋梗塞になりやすい“はずだ”」と言っているに過ぎないのであって,「本当に人間集団の中でそういう現象が起きているのか?」という問には答えていない.「人間集団の中でそういう現象が“本当に起きている”」ということを明快に示すことができるのが,「疫学研究」なのである.
このように,問いかけられた疑問に対して一度自分自身で考えてから説明を受けると理解が深まり,さらに類似の問題を解くことによって知識が定着していくと考えられる.そこで本書では,各章の最初に簡単な解説を行った後,「演習」で問題を解いたうえで解説を読んで理解し,各章末の「確認問題」で知識を定着するという構成になっている.疫学は公衆衛生学の基礎科学であり,人を対象とした医学研究の方法論として広く用いられている.学生の皆さんにとっては国家試験のための勉強はもちろんのこと,卒業研究や修士・博士課程で量的研究に取り組む際に必要となる学問である.また自治体や研究機関などで調査統計に関わる方々にとっては,その調査結果を正しく解釈し活用するために疫学の考え方は必須である.ぜひ本書の学習方法により疫学の考え方を身につけ,実践に活かす一助としていただければ幸甚である.
本書は「疫学入門演習」(東京医科歯科大学名誉教授 田中平三先生著)の内容を踏襲し,その改訂版としての位置づけでもある.疫学入門演習は私が大学生の頃から田中先生のご指導のもとで疫学を学んだ際のバイブル的な書であり,その隅々まで読み込んだことが,今の私の礎となっている.今回,その後継となる「演習問題で学ぶ疫学」の執筆を私にお任せくださったことは望外の喜びであり,田中先生には深甚なる謝意を捧げるとともに,今後のご健勝をお祈り申し上げたい.
2024 年7 月
国立保健医療科学院生涯健康研究部 部長
横山徹爾
目次
[総 論]
第1章 疫学の概要
A.疫学の基礎
1.疫学の語源
2.疫学の定義
3.疫学の対象
4.疫学の領域
B.疫学のサイクル
C.多重原因論
D.疫学と公衆衛生活動のステップ
第2章 疾病頻度の指標
A.率
B.危険曝露人口
C.患者(分子)の把握
D.疾病頻度の測定尺度
第3章 交絡変数とその調整
A.交絡変数
B.年齢調整死亡率と標準化死亡比
第4章 スクリーニング
A.目的・要件
B.評価指標
[研究デザインと因果関係の推理]
第5章 記述疫学と疫学的仮説の設定
A.記述疫学
B.疫学的仮説の設定
1.帰納的推理
2.演繹的推理
第6章 横断研究と生態学的研究
A.横断研究
B.生態学的研究
第7章 症例対照研究
A.定義・方法
B.分 析
C.交絡の調整
第8章 コホート研究
A.定義・方法
B.分 析
第9章 介入研究
A.定義・方法
B.臨床試験
C.分 析
1.並行法
2.クロスオーバー法
第10章 因果関係の推理
A.推理の過程
B.統計学的関連
C.近位因果関係と遠位因果関係
D.因果関係の判断条件
E.システマティックレビューとメタアナリシス
[疫学の応用]
第11章 歴史に学ぶ疫学の戦術(わが国における脳卒中の疫学的研究)
A.仮説設定の糸口―記述疫学―
B.脳卒中“臨床診断”の妥当性
C.横断研究による疫学的仮説の設定
D.症例対照研究による疫学的仮説の検定
E.コホート研究による疫学的仮説の検定
F.介入研究
G.脳卒中発生機序解明への道
第12章 政策と疫学
A.健康政策と PDCA サイクル
1.集団の健康評価(地域診断)
2.介入効果の予測と目標設定
3.政策(施策・事業)の選択と実施
4.政策(施策・事業)の評価
5.PDCA サイクル
B.国民健康づくり運動
[保健統計の基礎]
第13章 疾病頻度に関わる公的統計調査
A.平均寿命と生命表
1.平均寿命・平均余命
2.生命表
B.人口動態統計
C.患者調査,国民生活基礎調査
1.患者調査
2.国民生活基礎調査
D.国民健康・栄養調査
E.全国がん登録
F.国際疾病分類(ICD)
第14章 疫学で用いられる統計学の基礎
A.データの要約
1.データの種類
2.数量データの要約
3.質的データの要約
B.標本と母集団
C.点推定と区間推定
D.検 定
E.相関・回帰
F.多変量解析
1.重回帰分析
2.多重ロジスティックモデル
3.多変量 Cox 比例ハザードモデル
G.サンプルサイズ
1.高い精度で推定を行う
2.有意差(有意な関連)を検出する
まとめ問題
解答・解説
第1章 疫学の概要
A.疫学の基礎
1.疫学の語源
2.疫学の定義
3.疫学の対象
4.疫学の領域
B.疫学のサイクル
C.多重原因論
D.疫学と公衆衛生活動のステップ
第2章 疾病頻度の指標
A.率
B.危険曝露人口
C.患者(分子)の把握
D.疾病頻度の測定尺度
第3章 交絡変数とその調整
A.交絡変数
B.年齢調整死亡率と標準化死亡比
第4章 スクリーニング
A.目的・要件
B.評価指標
[研究デザインと因果関係の推理]
第5章 記述疫学と疫学的仮説の設定
A.記述疫学
B.疫学的仮説の設定
1.帰納的推理
2.演繹的推理
第6章 横断研究と生態学的研究
A.横断研究
B.生態学的研究
第7章 症例対照研究
A.定義・方法
B.分 析
C.交絡の調整
第8章 コホート研究
A.定義・方法
B.分 析
第9章 介入研究
A.定義・方法
B.臨床試験
C.分 析
1.並行法
2.クロスオーバー法
第10章 因果関係の推理
A.推理の過程
B.統計学的関連
C.近位因果関係と遠位因果関係
D.因果関係の判断条件
E.システマティックレビューとメタアナリシス
[疫学の応用]
第11章 歴史に学ぶ疫学の戦術(わが国における脳卒中の疫学的研究)
A.仮説設定の糸口―記述疫学―
B.脳卒中“臨床診断”の妥当性
C.横断研究による疫学的仮説の設定
D.症例対照研究による疫学的仮説の検定
E.コホート研究による疫学的仮説の検定
F.介入研究
G.脳卒中発生機序解明への道
第12章 政策と疫学
A.健康政策と PDCA サイクル
1.集団の健康評価(地域診断)
2.介入効果の予測と目標設定
3.政策(施策・事業)の選択と実施
4.政策(施策・事業)の評価
5.PDCA サイクル
B.国民健康づくり運動
[保健統計の基礎]
第13章 疾病頻度に関わる公的統計調査
A.平均寿命と生命表
1.平均寿命・平均余命
2.生命表
B.人口動態統計
C.患者調査,国民生活基礎調査
1.患者調査
2.国民生活基礎調査
D.国民健康・栄養調査
E.全国がん登録
F.国際疾病分類(ICD)
第14章 疫学で用いられる統計学の基礎
A.データの要約
1.データの種類
2.数量データの要約
3.質的データの要約
B.標本と母集団
C.点推定と区間推定
D.検 定
E.相関・回帰
F.多変量解析
1.重回帰分析
2.多重ロジスティックモデル
3.多変量 Cox 比例ハザードモデル
G.サンプルサイズ
1.高い精度で推定を行う
2.有意差(有意な関連)を検出する
まとめ問題
解答・解説