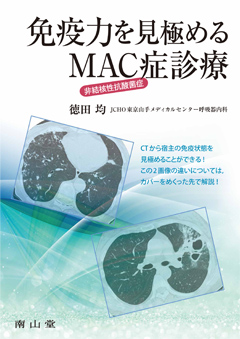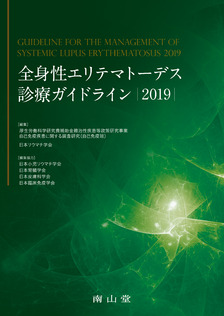免疫力を見極める 非結核性抗酸菌症(MAC症)診療
1版
JCHO東京山手メディカルセンター呼吸器内科 徳田 均 著
定価
8,800円(本体 8,000円 +税10%)
- B5判 240頁
- 2025年2月 発行
- ISBN 978-4-525-26601-1
非結核性抗酸菌症(MAC症)は免疫力で制御できる!
近年,非結核性抗酸菌症(MAC症)は呼吸器科医の悩みの種となっている.ガイドラインに従って治療をしてもなかなか菌が根絶できず,ようやく長い治療を終えてもすぐに再発して戻ってくる.かと思えば,特段の治療をせずとも,10年以上も健康に過ごす患者さんもいる.空洞と見間違えやすい気管支拡張症,見落としやすい肺癌の陰影,関節リウマチとの合併症例……などなど.
悩んでいるのは医師だけではない.患者は終わりの見えない長期服薬治療に不安を抱え,味覚障害などの副作用によって著しくQOLが損なわれている.
そのような悩みに真摯に向き合い,医師・患者の両方から高い評価を得ている著者が,どのようにすればMAC症をコントロールできるのか理論化を試みる!
1人1人の患者に丁寧に接することで見えてきたものとは? 免疫力,運動療法,結核病との比較……ガイドラインに書いていないけれども,本書を一読したあなたは思わず「その経験が自分にもある!」「それが知りたかった!」と膝を叩くことだろう.
著者20年の経験とわが国の結核病学の蓄積に基づく,まさに集大成とも言うべき一冊.
- 序文
- 本書の視点
- 目次
序文
肺非結核性抗酸菌症(nontuberculous mycobacteriosis:NTM症)は,近年わが国で増加が著しく,その治療困難性もあって,にわかに注目を集めている疾患である.
結核と異なり登録制ではないため,長く正確な実態が不明だったが,近年,医療施設へのアンケート調査,人口動態統計やレセプトデータからの推計,検査センターから提供された資料の解析などを基に,罹患率,有病率が明らかにされつつある.その罹患率は,結核の順調な逓減もあって結核を上回っていると推定される.わが国でも最大規模の慢性感染症として改めて取り組みが求められている.
この疾患については,伝染性はほぼなく,公衆衛生上の問題は少ないが,個々の患者の問題としては未解決の部分が多い.決定的な治療薬に乏しく,完全な制御が困難であるとされる.多くの例で長期の薬物治療が勧められているが,それでも中には再発を繰り返し,あるいは着実に進行し,肺が荒廃し死に到る例がある.一方,長年にわたってほとんど進展せず,自然治癒する例も少なくない.この経過の多様さが何に由来するかは未解明である.
治療についても大きな問題があり,国内外のガイドラインで「標準治療(CAM+EB+RFP)」が推奨されているが,治療期間の長さ,副作用の多さから,治療から脱落する例が少なくない.そのレジメンは過去20年間変わっておらず,そして実はエビデンスに基づくものでもない.
また,どんな例に治療が必要で,どんな例が観察だけでよいのか? 初発時,再燃時の適切な治療期間は? などについても,海外,日本ともエビデンスに基づいた指針はなく,現場の医師の判断に委ねられている.結核症が標準治療法とそのバリエーション,治療期間,治療中のさまざまな臨床的問題とそれらへの対処法について,エビデンスに基づいた指針が整備されていることとは対照的である.
最近ようやく,その大部分を占めるMAC症(Mycobacterium avium-intracellulare complex症)(注)については,その自然史,薬物治療の効果とその限界などについて報告が蓄積されてきた.それを基に,内外の専門家たちから,抗菌薬治療の限界を見据え,それ以外のさまざまな治療法,栄養療法,運動療法などの導入,また治療のアウトカムとして菌陰性化以外の指標の設定〔患者報告アウトカム(patient-reported outcome)など〕について,新しい提案がなされるようになった.しかしいまだ具体的な成果は少ない.
筆者は市中の総合病院の呼吸器科医師として,過去30年にわたって診療の場で多くの非結核性抗酸菌症の患者を診療してきた.その診療に当たっては,常に最新の学問的成果を参照しつつ,一方で何が患者にとってベストかを考えてさまざまに工夫をしてきた.
そのような経験,研究を踏まえて,本書で提供する診療のヒントは,これまでほとんど言及されなかったが,MAC症の病態を結核症と比較する視点にある.MACは結核菌と祖先を一にし,細菌学的,生化学的に結核菌ときわめて類似している.また病理学的にも,わが国での過去の多くの研究から,MAC症は結核症と基本的な病態は類似していることが明らかにされている.
その結核症の病態については,半世紀前にわが国の研究者たちが大きな展開を成し遂げた.結核症の複雑,多様な病態はその病理形態を押さえると整理できる,そしてその病理形態はX線画像からも読み取れるという,世界にも類を見ない達成である.有難いことにその達成は,今日われわれは,HRCTという武器で受け継ぐことができ,それを臨床に応用することができる.それを通じて,眼前の結核患者に起こっている病理学的事態,ひいては免疫学的病態を推定することが可能となった.
このような結核病学の成果は,上記の類似,共通点の多さから,MAC症にも応用可能である.HRCT所見の解読を通じて,その時点での病態=免疫学的動態を知り,それを診療に役立てることができる.筆者はこれを日々の臨床で実践して大きな成果を得ている.本書ではその成果を提示したい.これは,わが国はもとより,世界のどこからも提示されていない視点である.
慢性感染症において菌と宿主の免疫応答を見ていくうえでは,さまざまな因子,ストレス,栄養などが関与することは今日常識となりつつある.これらの視点も抗菌療法と同様に重要であり,これを意識したMAC症診療を行うべきとの主張は,近年欧米からも湧き起こっている.この視点も本書で提示したいことの一つである.
本書では,そのような立場に立って筆者が蓄積してきたMAC症診療の考え方を紹介していく.MAC症は,外からの菌の侵入によって起こる病気であり,長期にわたる薬物療法によってこの菌を根絶せねばならないという考え方は,もしあるとすれば誤りである.菌との共存を目指すべきであるし,それは十分可能である.そのためにはHRCTの読影を通じて患者の免疫学的病態を把握し,その患者のその時点での,そしてそこから起こるであろう事態を予測することが有効であり,そうすることでMAC症の大部分は制御可能であるというのが,現在の私の確信であり,それをこの本を通じてお伝えしたい.
注:最近,M. avium症とM. intracellulare症とは,分けて論ずることがわが国の学会から提案されている.その理由として,疫学,感染ルート,薬物感受性,予後などが微妙に異なることが挙げられている.しかし,治療の観点からいえば両者に大きな違いはないともされている.本書では主に治療を考えていくので,また過去の臨床研究はMAC症としてまとめて蓄積されてきていることから,MAC症として一括して論じる.
2024年11月
JCHO東京山手メディカルセンター呼吸器内科
徳田 均
結核と異なり登録制ではないため,長く正確な実態が不明だったが,近年,医療施設へのアンケート調査,人口動態統計やレセプトデータからの推計,検査センターから提供された資料の解析などを基に,罹患率,有病率が明らかにされつつある.その罹患率は,結核の順調な逓減もあって結核を上回っていると推定される.わが国でも最大規模の慢性感染症として改めて取り組みが求められている.
この疾患については,伝染性はほぼなく,公衆衛生上の問題は少ないが,個々の患者の問題としては未解決の部分が多い.決定的な治療薬に乏しく,完全な制御が困難であるとされる.多くの例で長期の薬物治療が勧められているが,それでも中には再発を繰り返し,あるいは着実に進行し,肺が荒廃し死に到る例がある.一方,長年にわたってほとんど進展せず,自然治癒する例も少なくない.この経過の多様さが何に由来するかは未解明である.
治療についても大きな問題があり,国内外のガイドラインで「標準治療(CAM+EB+RFP)」が推奨されているが,治療期間の長さ,副作用の多さから,治療から脱落する例が少なくない.そのレジメンは過去20年間変わっておらず,そして実はエビデンスに基づくものでもない.
また,どんな例に治療が必要で,どんな例が観察だけでよいのか? 初発時,再燃時の適切な治療期間は? などについても,海外,日本ともエビデンスに基づいた指針はなく,現場の医師の判断に委ねられている.結核症が標準治療法とそのバリエーション,治療期間,治療中のさまざまな臨床的問題とそれらへの対処法について,エビデンスに基づいた指針が整備されていることとは対照的である.
最近ようやく,その大部分を占めるMAC症(Mycobacterium avium-intracellulare complex症)(注)については,その自然史,薬物治療の効果とその限界などについて報告が蓄積されてきた.それを基に,内外の専門家たちから,抗菌薬治療の限界を見据え,それ以外のさまざまな治療法,栄養療法,運動療法などの導入,また治療のアウトカムとして菌陰性化以外の指標の設定〔患者報告アウトカム(patient-reported outcome)など〕について,新しい提案がなされるようになった.しかしいまだ具体的な成果は少ない.
筆者は市中の総合病院の呼吸器科医師として,過去30年にわたって診療の場で多くの非結核性抗酸菌症の患者を診療してきた.その診療に当たっては,常に最新の学問的成果を参照しつつ,一方で何が患者にとってベストかを考えてさまざまに工夫をしてきた.
そのような経験,研究を踏まえて,本書で提供する診療のヒントは,これまでほとんど言及されなかったが,MAC症の病態を結核症と比較する視点にある.MACは結核菌と祖先を一にし,細菌学的,生化学的に結核菌ときわめて類似している.また病理学的にも,わが国での過去の多くの研究から,MAC症は結核症と基本的な病態は類似していることが明らかにされている.
その結核症の病態については,半世紀前にわが国の研究者たちが大きな展開を成し遂げた.結核症の複雑,多様な病態はその病理形態を押さえると整理できる,そしてその病理形態はX線画像からも読み取れるという,世界にも類を見ない達成である.有難いことにその達成は,今日われわれは,HRCTという武器で受け継ぐことができ,それを臨床に応用することができる.それを通じて,眼前の結核患者に起こっている病理学的事態,ひいては免疫学的病態を推定することが可能となった.
このような結核病学の成果は,上記の類似,共通点の多さから,MAC症にも応用可能である.HRCT所見の解読を通じて,その時点での病態=免疫学的動態を知り,それを診療に役立てることができる.筆者はこれを日々の臨床で実践して大きな成果を得ている.本書ではその成果を提示したい.これは,わが国はもとより,世界のどこからも提示されていない視点である.
慢性感染症において菌と宿主の免疫応答を見ていくうえでは,さまざまな因子,ストレス,栄養などが関与することは今日常識となりつつある.これらの視点も抗菌療法と同様に重要であり,これを意識したMAC症診療を行うべきとの主張は,近年欧米からも湧き起こっている.この視点も本書で提示したいことの一つである.
本書では,そのような立場に立って筆者が蓄積してきたMAC症診療の考え方を紹介していく.MAC症は,外からの菌の侵入によって起こる病気であり,長期にわたる薬物療法によってこの菌を根絶せねばならないという考え方は,もしあるとすれば誤りである.菌との共存を目指すべきであるし,それは十分可能である.そのためにはHRCTの読影を通じて患者の免疫学的病態を把握し,その患者のその時点での,そしてそこから起こるであろう事態を予測することが有効であり,そうすることでMAC症の大部分は制御可能であるというのが,現在の私の確信であり,それをこの本を通じてお伝えしたい.
注:最近,M. avium症とM. intracellulare症とは,分けて論ずることがわが国の学会から提案されている.その理由として,疫学,感染ルート,薬物感受性,予後などが微妙に異なることが挙げられている.しかし,治療の観点からいえば両者に大きな違いはないともされている.本書では主に治療を考えていくので,また過去の臨床研究はMAC症としてまとめて蓄積されてきていることから,MAC症として一括して論じる.
2024年11月
JCHO東京山手メディカルセンター呼吸器内科
徳田 均
本書の視点
本書は,筆者が32年間在籍してきた現在の職場,JCHO東京山手メディカルセンター(旧称:社会保険中央総合病院)で経験してきた約120例のMAC症患者のうち,①全経過にわたって病歴,画像が入手でき,②背景疾患あり(RA・膠原病,肺結核後遺症,肺気腫症,間質性肺炎)は除外(RAについては第12章でまとめて論じた),③他の菌種(M. abcessus, M. lentiflavumなど)に菌交代が起こり,専門施設に治療を依頼した例は除外して,残った約50例について,改めて各例の全経過を,画像を中心に,菌の経過,検査値,肺機能を参照しつつ検討し直し,まとめたものである.
当然バイアスはある.首都圏の市中病院であり,健診発見の受診が多く,肺結核後遺症などの肺の基礎疾患ありは少ない.その結果,比較的軽症例に偏った患者構成になっているかもしれない.
しかしそれでも,私はこの本を世に問う価値は十分にあると考える.その理由は以下のとおりである.
①わが国では世界に類を見ない広範な胸部X線健診が行われており,そこで異常を発見された例は大部分がCT(世界最高の普及率)検査に回されている.そのような経路で診断されるMAC症,あるいはMAC症疑い(菌所見などの検討はなく,画像所見からそれが疑われるもの)が非常に多く,医療現場にはそういった患者が溢れている.そのような健診発見,無症状例について,その治療をどうするべきか? 観察だけでよいのか? 何の指針も存在しない.筆者は今回の一連の検討から,ある程度その問題につき成案を得ている.
②自験例の中には,多くはないが重症例もあり,中には致死的経過を取った例も若干例あり,その手前でなんとか制御できた例もある.一方,ほとんど進展せず,中には自然治癒を営む例も存在する.どんな例が重症化するのか,どんな例が穏やかな経過を取るのか,進展を制御するにはどうすればよいのか,症例を供覧しつつ読者と一緒に考えたい.
③基本的認識として,
1)MACは古くから存在し(300万年とも言われる),現在も自然界に遍在する微生物であり,現生人類(ヒト)は10万年前のその誕生からこの微生物と共存してきたと考えられる.新型コロナウイルスのような新しい病原体ではない.その共存の仕方はヒト遺伝子の中に組み込まれていると考えられる.
2)感染者は非常に広範に存在し,そのうち発症するのはごくわずかである.
以上を踏まえて本書で展開するのは,
1)MACは基本的には弱毒菌であり,悪化は大部分が宿主の過剰免疫応答による.
2)CTを精密に読影することで宿主免疫がこの微生物にどのように応答しているかを把握することができ,診療方針の決定に役立つ.
という視点である.このような視点はこれまでまったく語られることのなかったものである.
日本のNTM症の定義は,世界のそれとは大きく異なる.国際ガイドラインでは,NTM症は,咳,痰などの呼吸器症状,あるいは体重減少などの全身症状があることが診断の条件になっている.一方,わが国ではこの条件は取り除かれ,その結果,健診発見の無症状例が広範に含まれることになっている.
このことは,これらの無~軽症例の治療方針を考えるうえで,国際ガイドラインの方針をそのままに取り入れてはならないことを意味する.
先に述べたように,わが国は非常に広範に胸部X線健診(職域健診,住民健診など)が行われており,そこで見つかった異常陰影が次々とCT検査に回され,放射線科医によって,MAC症の疑いとされている.このような健診発見のNTM症の頻度は明らかではないが,都市部では半分以上が健診発見であるというのが筆者の実感である.健診によるこのような「発見」は意味があるのだろうか? これらの例はやがては発病に至るのだろうか? そうではなく多くの例が自然軽快していくのだろうか? まったく調べられていない.
ここで思い起こすべきは,潜在性の癌である.潜在性の甲状腺癌や前立腺癌が広範な健診で多数発見されており,その意義が問われている.またCTで見出された肺癌もその多くがきわめて緩慢にしか進展せず,これを発見して治療することで肺癌死亡が減るとは証明されていない.治療介入をしてもしなくても疫学的に見て生存率に差が出ない悪性腫瘍がこうして多数存在することは医学上の事実として広く認識されている.
健診による多数のNTM症「患者」の発見は,これと同様の事態である可能性があるが,調べられていないのでなんとも言えない.
当然バイアスはある.首都圏の市中病院であり,健診発見の受診が多く,肺結核後遺症などの肺の基礎疾患ありは少ない.その結果,比較的軽症例に偏った患者構成になっているかもしれない.
しかしそれでも,私はこの本を世に問う価値は十分にあると考える.その理由は以下のとおりである.
①わが国では世界に類を見ない広範な胸部X線健診が行われており,そこで異常を発見された例は大部分がCT(世界最高の普及率)検査に回されている.そのような経路で診断されるMAC症,あるいはMAC症疑い(菌所見などの検討はなく,画像所見からそれが疑われるもの)が非常に多く,医療現場にはそういった患者が溢れている.そのような健診発見,無症状例について,その治療をどうするべきか? 観察だけでよいのか? 何の指針も存在しない.筆者は今回の一連の検討から,ある程度その問題につき成案を得ている.
②自験例の中には,多くはないが重症例もあり,中には致死的経過を取った例も若干例あり,その手前でなんとか制御できた例もある.一方,ほとんど進展せず,中には自然治癒を営む例も存在する.どんな例が重症化するのか,どんな例が穏やかな経過を取るのか,進展を制御するにはどうすればよいのか,症例を供覧しつつ読者と一緒に考えたい.
③基本的認識として,
1)MACは古くから存在し(300万年とも言われる),現在も自然界に遍在する微生物であり,現生人類(ヒト)は10万年前のその誕生からこの微生物と共存してきたと考えられる.新型コロナウイルスのような新しい病原体ではない.その共存の仕方はヒト遺伝子の中に組み込まれていると考えられる.
2)感染者は非常に広範に存在し,そのうち発症するのはごくわずかである.
以上を踏まえて本書で展開するのは,
1)MACは基本的には弱毒菌であり,悪化は大部分が宿主の過剰免疫応答による.
2)CTを精密に読影することで宿主免疫がこの微生物にどのように応答しているかを把握することができ,診療方針の決定に役立つ.
という視点である.このような視点はこれまでまったく語られることのなかったものである.
日本のNTM症の定義は,世界のそれとは大きく異なる.国際ガイドラインでは,NTM症は,咳,痰などの呼吸器症状,あるいは体重減少などの全身症状があることが診断の条件になっている.一方,わが国ではこの条件は取り除かれ,その結果,健診発見の無症状例が広範に含まれることになっている.
このことは,これらの無~軽症例の治療方針を考えるうえで,国際ガイドラインの方針をそのままに取り入れてはならないことを意味する.
先に述べたように,わが国は非常に広範に胸部X線健診(職域健診,住民健診など)が行われており,そこで見つかった異常陰影が次々とCT検査に回され,放射線科医によって,MAC症の疑いとされている.このような健診発見のNTM症の頻度は明らかではないが,都市部では半分以上が健診発見であるというのが筆者の実感である.健診によるこのような「発見」は意味があるのだろうか? これらの例はやがては発病に至るのだろうか? そうではなく多くの例が自然軽快していくのだろうか? まったく調べられていない.
ここで思い起こすべきは,潜在性の癌である.潜在性の甲状腺癌や前立腺癌が広範な健診で多数発見されており,その意義が問われている.またCTで見出された肺癌もその多くがきわめて緩慢にしか進展せず,これを発見して治療することで肺癌死亡が減るとは証明されていない.治療介入をしてもしなくても疫学的に見て生存率に差が出ない悪性腫瘍がこうして多数存在することは医学上の事実として広く認識されている.
健診による多数のNTM症「患者」の発見は,これと同様の事態である可能性があるが,調べられていないのでなんとも言えない.
目次
0章 NTM症の疫学,自然史,治療後の経過
一言まとめ:MACの一般人口での既感染率は高く,膨大な感染者の一部が健診で発見されていることがわが国の増加の主因であろう.本来穏やかな経過を取る予後のよい疾患で,その半数以上で治療を必要とせず,自然治癒率も高い.
1章 MAC症の多彩な病像―免疫の視点からの解析
一言まとめ:MAC症には,肺野に肉芽腫を形成しきわめて緩慢な経過を取りしばしば自然消退する「肉芽腫型」と,浸潤性病変・空洞を形成し肺を破壊していく「浸出型」があり,その予後は異なり,治療方針も異なってくる.
2章 治療開始時期―治療はただちに始めるべきか,当面経過観察でよいのか?
一言まとめ:肉芽腫型が主である場合まずは経過を観察し,進展増悪があれば治療するwatchful waitingが標準的な対応である.空洞がある場合ただちに治療を始めるべきと推奨されるがその科学的根拠はない.空洞のタイプにもよる.
3章 MAC症の治療:レジメン,治療期間
一言まとめ:「標準治療」のレジメン,期間には科学的根拠はない.特にRFPについてはさまざまな負の問題が浮上しており使用されない流れとなっている.治療期間についてもエビデンスはなく,肉芽腫型で副作用が強い場合短めにしても何ら問題はない.丁寧な観察が肝要.
4章 空洞の考え方
一言まとめ:MAC症の空洞は一律に強力な治療を行う必要はない.肉芽腫型の空洞は制御は容易なことが多く,一方周囲に浸出性病変を伴う空洞は強力な治療を必要とする.気管支の嚢状拡張を空洞と誤認しないことも大切である.
5章 治療困難例にどう対処するか?
一言まとめ:肉芽腫型で年の単位で拡大していく場合は,その都度の短期化学療法に加えて運動療法,ストレスの除去などの生活指導でよい.一方浸出型で週~月の単位で進行する場合は,多剤治療,必要に応じて短期間のステロイドも考慮する.
6章 再発にどう対処するか?
一言まとめ:MAC症の治療後再発は特にNB型で多い.その75%は再感染である.初回の化療を延長しても再発率は低下しない.再発は起こってからの治療でよい.そもそも観察だけでよい場合も多い.
7章 運動と栄養の重要性
一言まとめ:治療抵抗性,もしくは再発を繰り返す場合,薬物療法だけではこれを制御できない.規則正しい運動(ウォーキング)の慢性炎症性疾患における有効性は今や国際的に確立されている.栄養療法も劣らず重要である.
8章 MAC症の治療目標
一言まとめ:菌陰性化を治療の至上目標とすることは時にいたずらに患者を苦しめ,患者の幸福を目指すべき医療のありかたとは背馳する.癌などの他疾患と同様に,長期生存,良好な肺機能,良好なQOLを目標とすべきである.
9章 自然経過で治癒するMAC症
一言まとめ:MAC症の自然治癒は10~20%で起こる.それだけヒトはMACと共存する能力を持っていると言える.患者が本来の免疫力が発揮できるよう環境を整えることも医師の仕事の一つである.
10章 MAC症と気管支拡張症
一言まとめ:MAC症は高頻度に気管支拡張症を合併する.MAC症という病気の本質的な展開様式の一部であり,これに対して化療や宿主免疫は必ずしも有効でない.しかし適切に対処すれば恐れる必要はない.
11章 MAC症と肺癌
一言まとめ:MAC症には肺癌が合併しやすい.最大の問題は定期的な観察中に肺癌が出現してもMAC症陰影の中に紛れて発見が遅れがちということである.常にそれが起こりうるということを念頭に注意深い読影と対処が求められる.
12章 RAに合併するMAC症
一言まとめ:RA患者にはMAC症が多い.RAには高率に気道病変,間質性肺炎が合併しこれらがMAC症の母地となるためである.しかし適切に対処すれば予後は一般人と同じである.生物学的製剤など必要な治療は行ってよい.
一言まとめ:MACの一般人口での既感染率は高く,膨大な感染者の一部が健診で発見されていることがわが国の増加の主因であろう.本来穏やかな経過を取る予後のよい疾患で,その半数以上で治療を必要とせず,自然治癒率も高い.
1章 MAC症の多彩な病像―免疫の視点からの解析
一言まとめ:MAC症には,肺野に肉芽腫を形成しきわめて緩慢な経過を取りしばしば自然消退する「肉芽腫型」と,浸潤性病変・空洞を形成し肺を破壊していく「浸出型」があり,その予後は異なり,治療方針も異なってくる.
2章 治療開始時期―治療はただちに始めるべきか,当面経過観察でよいのか?
一言まとめ:肉芽腫型が主である場合まずは経過を観察し,進展増悪があれば治療するwatchful waitingが標準的な対応である.空洞がある場合ただちに治療を始めるべきと推奨されるがその科学的根拠はない.空洞のタイプにもよる.
3章 MAC症の治療:レジメン,治療期間
一言まとめ:「標準治療」のレジメン,期間には科学的根拠はない.特にRFPについてはさまざまな負の問題が浮上しており使用されない流れとなっている.治療期間についてもエビデンスはなく,肉芽腫型で副作用が強い場合短めにしても何ら問題はない.丁寧な観察が肝要.
4章 空洞の考え方
一言まとめ:MAC症の空洞は一律に強力な治療を行う必要はない.肉芽腫型の空洞は制御は容易なことが多く,一方周囲に浸出性病変を伴う空洞は強力な治療を必要とする.気管支の嚢状拡張を空洞と誤認しないことも大切である.
5章 治療困難例にどう対処するか?
一言まとめ:肉芽腫型で年の単位で拡大していく場合は,その都度の短期化学療法に加えて運動療法,ストレスの除去などの生活指導でよい.一方浸出型で週~月の単位で進行する場合は,多剤治療,必要に応じて短期間のステロイドも考慮する.
6章 再発にどう対処するか?
一言まとめ:MAC症の治療後再発は特にNB型で多い.その75%は再感染である.初回の化療を延長しても再発率は低下しない.再発は起こってからの治療でよい.そもそも観察だけでよい場合も多い.
7章 運動と栄養の重要性
一言まとめ:治療抵抗性,もしくは再発を繰り返す場合,薬物療法だけではこれを制御できない.規則正しい運動(ウォーキング)の慢性炎症性疾患における有効性は今や国際的に確立されている.栄養療法も劣らず重要である.
8章 MAC症の治療目標
一言まとめ:菌陰性化を治療の至上目標とすることは時にいたずらに患者を苦しめ,患者の幸福を目指すべき医療のありかたとは背馳する.癌などの他疾患と同様に,長期生存,良好な肺機能,良好なQOLを目標とすべきである.
9章 自然経過で治癒するMAC症
一言まとめ:MAC症の自然治癒は10~20%で起こる.それだけヒトはMACと共存する能力を持っていると言える.患者が本来の免疫力が発揮できるよう環境を整えることも医師の仕事の一つである.
10章 MAC症と気管支拡張症
一言まとめ:MAC症は高頻度に気管支拡張症を合併する.MAC症という病気の本質的な展開様式の一部であり,これに対して化療や宿主免疫は必ずしも有効でない.しかし適切に対処すれば恐れる必要はない.
11章 MAC症と肺癌
一言まとめ:MAC症には肺癌が合併しやすい.最大の問題は定期的な観察中に肺癌が出現してもMAC症陰影の中に紛れて発見が遅れがちということである.常にそれが起こりうるということを念頭に注意深い読影と対処が求められる.
12章 RAに合併するMAC症
一言まとめ:RA患者にはMAC症が多い.RAには高率に気道病変,間質性肺炎が合併しこれらがMAC症の母地となるためである.しかし適切に対処すれば予後は一般人と同じである.生物学的製剤など必要な治療は行ってよい.