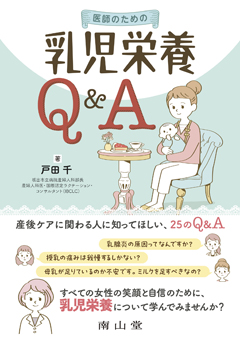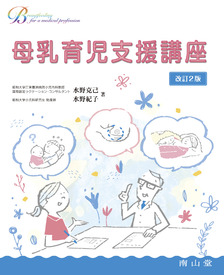医師のための乳児栄養Q&A
1版
坂出市立病院産婦人科 部長/
産婦人科医・国際認定ラクテーション・コンサルタント(IBCLC)
戸田 千 著
定価
3,520円(本体 3,200円 +税10%)
- A5判 242頁
- 2024年4月 発行
- ISBN 978-4-525-33661-5
根拠に基づいた乳児栄養の情報を,たっぷりまとめました
産後の女性と赤ちゃんを支えるためには,医療従事者が正確な情報を提供することが必要不可欠です.
そこで本書では,産婦人科医でありIBCLC(国際認定ラクテーション・コンサルタント)である著者が,医療従事者が知っておきたい科学的根拠に基づいた乳児栄養の情報を,インフォグラフィックも交えてたっぷりまとめました.乳腺炎,授乳姿勢,補足など,特に重要な話題を取り上げ,最新のエビデンスも盛り込みながら解説しています.
産婦人科医,小児科医はもちろん,助産師,看護師,保健師など,産後の女性と接する機会のあるすべての医療従事者に手に取ってほしい一冊です.
- 序文
- 目次
- Webインタビュー(前編)
- Webインタビュー(後編)
序文
乳児栄養の本を手に取ってくださってありがとうございます.
私は国際認定ラクテーション・コンサルタント(IBCLC)・産婦人科専門医です.IBCLC とは予防的なヘルスケアに焦点を当て,女性たちが赤ちゃんの育児で困ったときにセルフケアができるように問題解決の方法を示して意志決定できるよう支援し,楽に生活することを目指す乳児栄養(特に母乳育児)の専門家です.
母子の健康のためにWHO/UNICEF は多くの科学的根拠から,可能ならば生後6ヵ月は母乳だけで赤ちゃんを育てることなどを推奨しています.母乳育児とは単なる本能行動ではなくて,適切な方法を学んで練習して習得する行動でもあります.母乳育児支援の教科書も,英語ばかりでなくて最近は日本語も増えてきました.今までは赤ちゃんを中心とした内容がほとんどでしたので,この本では育児する女性たちが自己効力感を感じながら育児する立場を重視しました.母子のペアに起きる問題では主体を母と記し,それ以外の場面では「女性」と記しています.乳児栄養のグローバルスタンダードは母乳育児です.母子の人権を尊重しながら,母乳育児を希望した女性が赤ちゃんを育てるのに役立つ知識・技術や手段を示しています.
タイトルに「医師のための」を冠したのは,楽な母乳育児(一滴飲めば母乳育児です)を目指していくのに医師の参加が不可欠だからです.
分娩前後の数日間の過ごし方で出る母乳の量は大きく変わります.赤ちゃんの栄養不足は避けなければなりませんから,母子の快適さを保ちながら過不足ない母乳の量を得るために産後すぐのケアは重要です.医師が母子の乳児栄養に詳しくなれば産院など施設全体で共有する知識のアップデートや,産後の生活に影響するクリティカルパスなどシステム運営のパラダイムシフトにつながることでしょう.もちろん実質的な読者として女性を診療するすべての科と,産後ケアに関わるIBCLC をはじめとしたすべての職種を想定しています.
乳児用調整乳(粉ミルクや液体ミルク)を使用する際の支援には科学的根拠が少ないので,ミルクを使う場合には一例一例をどう観察して評価・支援していくかの視点から記しています.
インターネットの普及で,夜間に授乳しながら会話できるようになり,自分の推しと会話できる機会が生まれましたが,同時に不適切な情報がまるで王道であるかのように伝えられることも増えています.そこで,女性たちがどのような情報をインターネットから得ているかも示しました.
乳児栄養は母乳で育てるかミルクで育てるかという「物の話」だけではないです.女性たちがどのようにわが子と関わっていくかの,最初の大切な一歩を経験する機会でもあります.女性たちが自分の選んだ栄養法で,自信をもって楽な育児ができれば母子の笑顔が増えます.
この本の制作に当たって,IBCLC・小児科医の石井真美さんを初めとして,ここに書き切れない多くのIBCLC などの友人たちが内容や伝え方を吟味してくれました.さらに,南山堂の小池さんを初めとした編集者の皆さまからはこの本のために沢山の愛情を注いでいただきました.母子の笑顔を守るために関わってくださったすべての方,そして母乳外来などで出会った母子の皆さまに心より感謝します.
2024年3月
戸田 千
私は国際認定ラクテーション・コンサルタント(IBCLC)・産婦人科専門医です.IBCLC とは予防的なヘルスケアに焦点を当て,女性たちが赤ちゃんの育児で困ったときにセルフケアができるように問題解決の方法を示して意志決定できるよう支援し,楽に生活することを目指す乳児栄養(特に母乳育児)の専門家です.
母子の健康のためにWHO/UNICEF は多くの科学的根拠から,可能ならば生後6ヵ月は母乳だけで赤ちゃんを育てることなどを推奨しています.母乳育児とは単なる本能行動ではなくて,適切な方法を学んで練習して習得する行動でもあります.母乳育児支援の教科書も,英語ばかりでなくて最近は日本語も増えてきました.今までは赤ちゃんを中心とした内容がほとんどでしたので,この本では育児する女性たちが自己効力感を感じながら育児する立場を重視しました.母子のペアに起きる問題では主体を母と記し,それ以外の場面では「女性」と記しています.乳児栄養のグローバルスタンダードは母乳育児です.母子の人権を尊重しながら,母乳育児を希望した女性が赤ちゃんを育てるのに役立つ知識・技術や手段を示しています.
タイトルに「医師のための」を冠したのは,楽な母乳育児(一滴飲めば母乳育児です)を目指していくのに医師の参加が不可欠だからです.
分娩前後の数日間の過ごし方で出る母乳の量は大きく変わります.赤ちゃんの栄養不足は避けなければなりませんから,母子の快適さを保ちながら過不足ない母乳の量を得るために産後すぐのケアは重要です.医師が母子の乳児栄養に詳しくなれば産院など施設全体で共有する知識のアップデートや,産後の生活に影響するクリティカルパスなどシステム運営のパラダイムシフトにつながることでしょう.もちろん実質的な読者として女性を診療するすべての科と,産後ケアに関わるIBCLC をはじめとしたすべての職種を想定しています.
乳児用調整乳(粉ミルクや液体ミルク)を使用する際の支援には科学的根拠が少ないので,ミルクを使う場合には一例一例をどう観察して評価・支援していくかの視点から記しています.
インターネットの普及で,夜間に授乳しながら会話できるようになり,自分の推しと会話できる機会が生まれましたが,同時に不適切な情報がまるで王道であるかのように伝えられることも増えています.そこで,女性たちがどのような情報をインターネットから得ているかも示しました.
乳児栄養は母乳で育てるかミルクで育てるかという「物の話」だけではないです.女性たちがどのようにわが子と関わっていくかの,最初の大切な一歩を経験する機会でもあります.女性たちが自分の選んだ栄養法で,自信をもって楽な育児ができれば母子の笑顔が増えます.
この本の制作に当たって,IBCLC・小児科医の石井真美さんを初めとして,ここに書き切れない多くのIBCLC などの友人たちが内容や伝え方を吟味してくれました.さらに,南山堂の小池さんを初めとした編集者の皆さまからはこの本のために沢山の愛情を注いでいただきました.母子の笑顔を守るために関わってくださったすべての方,そして母乳外来などで出会った母子の皆さまに心より感謝します.
2024年3月
戸田 千
目次
第 1 章 乳腺炎~経験則と科学的根拠のはざま~
1 お宮参りで乳腺炎?
2 お正月休みに乳腺炎になったら?
3 乳腺炎のときの病院受診のタイミングは?
4 授乳中の薬は?
5 母乳が出すぎてつらいです
6 乳腺炎の適切なケアをスタッフ間で共有するために
第 2 章 授乳姿勢~解剖学と生理学の応用~
授乳姿勢・赤ちゃんの吸着の章を読むときのご提案
すぐに役立つ具体的で簡単な支援方法
1 白斑ができて痛い!
2 授乳の痛みは仕方ないの?
3 授乳回数を減らすコツは?
4 おっぱいがカチカチになってしまう
5 乳腺炎を早く治すための授乳姿勢は?
適切な授乳姿勢とは?
6 楽な授乳はどんな姿勢?
7 楽な授乳方法を動画で見たいです
授乳を楽にするパラダイムシフトのために
8 授乳姿勢と吸着でどんな問題が解決しますか?
9 授乳姿勢や吸着に関する参考文献は?
第 3 章 乳児の栄養不足を考える~母乳は受注生産~
1 赤ちゃんが泣くのは,母乳が足りないから?
2 母乳と睡眠にはどんな関係がある?
3 母乳が足りているのか不安です
4 科学的根拠に基づいた補足の方法
5 産後の入院中に母乳育児を楽にする支援のコツ
6 飲み終わっても泣くのは,母乳が足りないから?
7 混合栄養です.人工乳の減らし方は?
8 どうして母乳育児を支援するのか?
9 ミルクの調乳方法は?
第 4 章 赤ちゃんとの生活を楽にするために
1 生活の問題? 医学的な問題?
2 赤ちゃんが泣きやまないんです
3 母乳や人工乳が足りないのですか?
4 授乳が痛いです
5 寝不足がつらいです
6 こんなはずではなかったです
乳児栄養がわかるインフォグラフィック
「赤ちゃんが泣きやまないんです」と言われたら
「母乳が足りないのですか?」と聞かれたら その1
「母乳が足りないのですか?」と聞かれたら その2
「授乳が痛いです」と言われたら
「寝不足がつらいです」と言われたら
「産む前に知っておくといいことはありますか?」と聞かれたら
家族や周りの人にも伝えておきたい情報 母乳育児の利点編
家族や周りの人にも伝えておきたい情報 母乳育児の仕組み編
索 引
1 お宮参りで乳腺炎?
2 お正月休みに乳腺炎になったら?
3 乳腺炎のときの病院受診のタイミングは?
4 授乳中の薬は?
5 母乳が出すぎてつらいです
6 乳腺炎の適切なケアをスタッフ間で共有するために
第 2 章 授乳姿勢~解剖学と生理学の応用~
授乳姿勢・赤ちゃんの吸着の章を読むときのご提案
すぐに役立つ具体的で簡単な支援方法
1 白斑ができて痛い!
2 授乳の痛みは仕方ないの?
3 授乳回数を減らすコツは?
4 おっぱいがカチカチになってしまう
5 乳腺炎を早く治すための授乳姿勢は?
適切な授乳姿勢とは?
6 楽な授乳はどんな姿勢?
7 楽な授乳方法を動画で見たいです
授乳を楽にするパラダイムシフトのために
8 授乳姿勢と吸着でどんな問題が解決しますか?
9 授乳姿勢や吸着に関する参考文献は?
第 3 章 乳児の栄養不足を考える~母乳は受注生産~
1 赤ちゃんが泣くのは,母乳が足りないから?
2 母乳と睡眠にはどんな関係がある?
3 母乳が足りているのか不安です
4 科学的根拠に基づいた補足の方法
5 産後の入院中に母乳育児を楽にする支援のコツ
6 飲み終わっても泣くのは,母乳が足りないから?
7 混合栄養です.人工乳の減らし方は?
8 どうして母乳育児を支援するのか?
9 ミルクの調乳方法は?
第 4 章 赤ちゃんとの生活を楽にするために
1 生活の問題? 医学的な問題?
2 赤ちゃんが泣きやまないんです
3 母乳や人工乳が足りないのですか?
4 授乳が痛いです
5 寝不足がつらいです
6 こんなはずではなかったです
乳児栄養がわかるインフォグラフィック
「赤ちゃんが泣きやまないんです」と言われたら
「母乳が足りないのですか?」と聞かれたら その1
「母乳が足りないのですか?」と聞かれたら その2
「授乳が痛いです」と言われたら
「寝不足がつらいです」と言われたら
「産む前に知っておくといいことはありますか?」と聞かれたら
家族や周りの人にも伝えておきたい情報 母乳育児の利点編
家族や周りの人にも伝えておきたい情報 母乳育児の仕組み編
索 引
Webインタビュー(前編)
「医師のための乳児栄養Q&A」Webインタビュー(前編)
Q1. 戸田先生はこれまで長年にわたり、乳児栄養に関して講演やブログ、SNSなどで発信され続けてきました。先生が乳児栄養について情報発信をされるようになったきっかけを教えてください。
最初は、遠方にいる友人が出産したことがきっかけでした。その友人が初めての育児で四苦八苦していたときに、メールで質問をもらっては答えていたのです。ある時、この答えは沢山の人が知りたいものではないだろうか?と気付き、2005年に母乳育児支援のためのブログ「やわらかな風の吹く場所に」を開設しました。
その子には、10ヶ月になった時に初めてお会いしました。届けたメッセージで親子はより安心して毎日を送ることができていることを確認できました。
その当時に私が問題解決のための根拠として頼りにしていたのは、ラ・レーチェ・リーグの「だれでもできる母乳育児」などの数冊の本そして、自分の支援経験だけでした。
2006年に、私はIBCLC(国際認定ラクテーション・コンサルタント)に認定されました。本書でも解説していますが、IBCLCとは人権に関する国際条約などを遵守しながら、乳児栄養や赤ちゃんを育てる女性の健康を守るための予防医学の専門家です。IBLCE(IBCLCを認定している団体です)が求めるIBCLCの活動は、「以下の臨床能力(IBCLCの臨床能力・IBCLCの業務範囲・IBCLCの職務行動規範)を有し,業務範囲,職務行動規範に基づいて実践を行います」であると記されています。試験範囲は妊娠・出産・授乳・新生児や乳児の健康・女性の健康、WHOの健康政策、統計学、コミュニケーションスキルなどを網羅しています。範囲としては狭くても、試験ではとても深い部分まで尋ねられるので、受験の際には医師国家試験よりもヘビーに感じられました。
IBCLCになってからは、次の資格更新のために単位が取得できる学習会を受講したり、自身も講師を務めたりする中で、参考文献を示せる情報提供の重要さを学ぶようになりました。
それに伴い、IBCLCとしての職務行動規範の中で発信していくために、ブログにおいても教科書や論文などの参考文献を示すことに注意するようにしています。
読んだ人が安心して読むことができる言葉遣いで、科学的根拠があり、利益相反のない情報を提供する、ということを目指してブログの記事は書いています。母乳かミルクかという話よりも、赤ちゃんとその子を育てる女性の関係を支えるための情報発信を心がけてきました。
Q2.情報発信を続けるということは、とても根気のいることかと思います。継続にあたってのモチベーションはなんだったのでしょうか?
モチベーションのひとつは、十分にケアされて母乳育児ができている女性たちは、補足の必要性の有無にかかわらず、とても楽そうにしている、ということ。
編集者さんに「『楽そう』というのは、『楽しそう』ということですよね?」と尋ねられたこともあります。私は答えました。「楽(らく)そうでーす」と。
つまり、十分にケアをされて母乳育児をしている女性たちは、「楽しそう」でもありますが、根本的に「楽そう」なのです。
一方で、同じ時期の新生児を育てているのにもかかわらず、あちこちの痛みや赤ちゃんの泣き声に悩んで眉間に皺を寄せて母乳育児をしている女性や,どのくらいのミルクを使っていいのか悩みながら、手探りで混合栄養をしている女性もいます。特に混合栄養は、頼りになるガイドラインなどのルールを作るのが困難な、個人差の多い育児の形です。
1か月健診などでは、体重が増えているかどうかは伝えても、どのくらいのミルクの量が必要であるか、母乳がどれくらい出ているかなどの具体的な評価やフォローのない施設がほとんどです。その結果として、赤ちゃんを育てながらいつも困っている女性がいるのです。健診で計測した数字に問題がないと、赤ちゃんを育てる女性たちの悩みが医療者にはなかなか届きません。そして、女性の悩みが医療者に届いていないということは、大きな問題です。
楽そうに、そして楽しそうに育児している女性と、つらそうに育児をしている女性の差は,どこにあるのでしょうか。明らかに存在する差としては、施設が提供するケアの違いがあります。施設のケアの違いによるのであれば、医療者がケアを変えることで、女性たちの悩みを軽くできるはずです。
また、情報発信を続けるうえで大きな影響があったのは、災害時における乳児栄養の問題です。2004年10月23日には、新潟県中越地震が起きました。私はそのとき、被災者の方が校庭に「ミルク」と文字を描いて支援を求めていらっしゃったのを、テレビの画面で苦しい気持ちになりながら見ていました。
そして、そのときの記憶が残っていたため、2011年3月11日の東日本大震災の際には、地震発生後すぐから、乳幼児を守るための情報をTwitter(現X)とブログで発信することにしました。
JALC(NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会)もこういった情報発信は行っていますが、情報を妥当なものとするためにピアレビュー(査読)を重ねてから発信することとなっています。そのため、JALCの情報発信の速さに限界があります。そこで、私個人でどんどん情報を発信することにしたのです。
当日、私は埼玉出張予定でしたが、震災の影響で行くことができなくなり、取っていた勤務先の休みがそのまま情報発信の文章を書く時間となりました。2~3時間寝ては起きて、調べ物をしてTwitter(現X)やブログの記事を書く、ということを繰り返しました。当時、震災・津波を生き延びた赤ちゃんの健康を守るための乳児栄養についての情報は様々なものが錯綜していました。IFEcore group(Infant Feeding in Emergencies core group)等が発信している母子を守るための科学的根拠に基づいた世界基準の情報と、善意のように見えていても実際は何らかの商品の営業活動である情報とが混在していたのです。赤ちゃんにとっての栄養の問題は、特に災害時には命に繋がる深刻な問題であることが、この頃はあまり知られていませんでした。
1人の人間による情報発信は微々たるものです。ですが時間が経つと、JALCやラ・レーチェ・リーグ(母親同士のピアカウンセリングを行っているボランティア団体)などによる、科学的根拠に基づいていて、伝える際の言葉づかいなどにも繊細に注意を払った情報が揃っていきました。そして、そのような情報の拡散には、多くの心ある医師・助産師・看護師などの医療従事者が手を貸してくれました。
このときに拡散できた重要な情報の1つに、「カップ授乳」があります。そもそも乳児用ミルクが不足しないようにすることも重要ですが、赤ちゃんが乳児用ミルク飲む際の環境が清潔なものであることも重要です。しかし、水が貴重なものとなる被災地では、清潔な哺乳瓶を用意することは困難になります。そこで、清潔な哺乳瓶が準備できない状況でも、赤ちゃんに安全に乳児用ミルクを飲んでもらい、赤ちゃんの命を守るための大切な技術として、「カップ授乳」と呼ばれる、紙コップや湯のみで授乳する方法があります。産婦人科医師有志が被災地に届けた救援物資の中に、カップ授乳の方法を記した紙を入れてもらうことで、この情報を被災地の赤ちゃんと女性に届けることができました。
乳児栄養についての悩みは、当事者である赤ちゃんや女性にとっては常に存在するものではありますが、多くの医療従事者にとっては、災害時などの切羽詰まったタイミングでなければ気付きにくいニッチな悩みごとでもあります。そのような悩みが存在すると気付いた者の責務だと思って,私は情報発信を続けています。それが産婦人科医師の仕事かどうかは、いまだに私の頭の中でも答えは出ていません。ですが、このような情報発信をすることで楽になったり幸せになったり人がいて、そしてそのことを伝えようとしている人があまりいないのであれば、やはりこれは気付いた者の重要なミッションだと思い、情報発信を続けています。
こうしたことを続けてきたモチベーションの中には、科学・医学・支援経験とは別の世界もあります。それは、子どもの頃からの私のヒーローだったアニメキャラクターの声をあてた役者さんとの出会いです。その人とはTwitter(現X)で出会いました。彼は、赤ちゃんを守る情報をいつもリツイートしてくれていました。この応援は私にとってとても大きいものでした。私のブログの読者層、が一気に広がるきっかけになったからです。
後に、その人は講演でおっしゃっていました。5歳の時に、乳飲み子だった弟を空襲から逃がすことはできたものの、弟はその後、栄養失調で亡くなってしまったのだと。母乳や栄養が足りないせいで、子どもが不健康になったり亡くなったりするような世界はあってはならない。この信念を、私はこの人からも受け取りました。
Q1. 戸田先生はこれまで長年にわたり、乳児栄養に関して講演やブログ、SNSなどで発信され続けてきました。先生が乳児栄養について情報発信をされるようになったきっかけを教えてください。
最初は、遠方にいる友人が出産したことがきっかけでした。その友人が初めての育児で四苦八苦していたときに、メールで質問をもらっては答えていたのです。ある時、この答えは沢山の人が知りたいものではないだろうか?と気付き、2005年に母乳育児支援のためのブログ「やわらかな風の吹く場所に」を開設しました。
その子には、10ヶ月になった時に初めてお会いしました。届けたメッセージで親子はより安心して毎日を送ることができていることを確認できました。
その当時に私が問題解決のための根拠として頼りにしていたのは、ラ・レーチェ・リーグの「だれでもできる母乳育児」などの数冊の本そして、自分の支援経験だけでした。
2006年に、私はIBCLC(国際認定ラクテーション・コンサルタント)に認定されました。本書でも解説していますが、IBCLCとは人権に関する国際条約などを遵守しながら、乳児栄養や赤ちゃんを育てる女性の健康を守るための予防医学の専門家です。IBLCE(IBCLCを認定している団体です)が求めるIBCLCの活動は、「以下の臨床能力(IBCLCの臨床能力・IBCLCの業務範囲・IBCLCの職務行動規範)を有し,業務範囲,職務行動規範に基づいて実践を行います」であると記されています。試験範囲は妊娠・出産・授乳・新生児や乳児の健康・女性の健康、WHOの健康政策、統計学、コミュニケーションスキルなどを網羅しています。範囲としては狭くても、試験ではとても深い部分まで尋ねられるので、受験の際には医師国家試験よりもヘビーに感じられました。
IBCLCになってからは、次の資格更新のために単位が取得できる学習会を受講したり、自身も講師を務めたりする中で、参考文献を示せる情報提供の重要さを学ぶようになりました。
それに伴い、IBCLCとしての職務行動規範の中で発信していくために、ブログにおいても教科書や論文などの参考文献を示すことに注意するようにしています。
読んだ人が安心して読むことができる言葉遣いで、科学的根拠があり、利益相反のない情報を提供する、ということを目指してブログの記事は書いています。母乳かミルクかという話よりも、赤ちゃんとその子を育てる女性の関係を支えるための情報発信を心がけてきました。
Q2.情報発信を続けるということは、とても根気のいることかと思います。継続にあたってのモチベーションはなんだったのでしょうか?
モチベーションのひとつは、十分にケアされて母乳育児ができている女性たちは、補足の必要性の有無にかかわらず、とても楽そうにしている、ということ。
編集者さんに「『楽そう』というのは、『楽しそう』ということですよね?」と尋ねられたこともあります。私は答えました。「楽(らく)そうでーす」と。
つまり、十分にケアをされて母乳育児をしている女性たちは、「楽しそう」でもありますが、根本的に「楽そう」なのです。
一方で、同じ時期の新生児を育てているのにもかかわらず、あちこちの痛みや赤ちゃんの泣き声に悩んで眉間に皺を寄せて母乳育児をしている女性や,どのくらいのミルクを使っていいのか悩みながら、手探りで混合栄養をしている女性もいます。特に混合栄養は、頼りになるガイドラインなどのルールを作るのが困難な、個人差の多い育児の形です。
1か月健診などでは、体重が増えているかどうかは伝えても、どのくらいのミルクの量が必要であるか、母乳がどれくらい出ているかなどの具体的な評価やフォローのない施設がほとんどです。その結果として、赤ちゃんを育てながらいつも困っている女性がいるのです。健診で計測した数字に問題がないと、赤ちゃんを育てる女性たちの悩みが医療者にはなかなか届きません。そして、女性の悩みが医療者に届いていないということは、大きな問題です。
楽そうに、そして楽しそうに育児している女性と、つらそうに育児をしている女性の差は,どこにあるのでしょうか。明らかに存在する差としては、施設が提供するケアの違いがあります。施設のケアの違いによるのであれば、医療者がケアを変えることで、女性たちの悩みを軽くできるはずです。
また、情報発信を続けるうえで大きな影響があったのは、災害時における乳児栄養の問題です。2004年10月23日には、新潟県中越地震が起きました。私はそのとき、被災者の方が校庭に「ミルク」と文字を描いて支援を求めていらっしゃったのを、テレビの画面で苦しい気持ちになりながら見ていました。
そして、そのときの記憶が残っていたため、2011年3月11日の東日本大震災の際には、地震発生後すぐから、乳幼児を守るための情報をTwitter(現X)とブログで発信することにしました。
JALC(NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会)もこういった情報発信は行っていますが、情報を妥当なものとするためにピアレビュー(査読)を重ねてから発信することとなっています。そのため、JALCの情報発信の速さに限界があります。そこで、私個人でどんどん情報を発信することにしたのです。
当日、私は埼玉出張予定でしたが、震災の影響で行くことができなくなり、取っていた勤務先の休みがそのまま情報発信の文章を書く時間となりました。2~3時間寝ては起きて、調べ物をしてTwitter(現X)やブログの記事を書く、ということを繰り返しました。当時、震災・津波を生き延びた赤ちゃんの健康を守るための乳児栄養についての情報は様々なものが錯綜していました。IFEcore group(Infant Feeding in Emergencies core group)等が発信している母子を守るための科学的根拠に基づいた世界基準の情報と、善意のように見えていても実際は何らかの商品の営業活動である情報とが混在していたのです。赤ちゃんにとっての栄養の問題は、特に災害時には命に繋がる深刻な問題であることが、この頃はあまり知られていませんでした。
1人の人間による情報発信は微々たるものです。ですが時間が経つと、JALCやラ・レーチェ・リーグ(母親同士のピアカウンセリングを行っているボランティア団体)などによる、科学的根拠に基づいていて、伝える際の言葉づかいなどにも繊細に注意を払った情報が揃っていきました。そして、そのような情報の拡散には、多くの心ある医師・助産師・看護師などの医療従事者が手を貸してくれました。
このときに拡散できた重要な情報の1つに、「カップ授乳」があります。そもそも乳児用ミルクが不足しないようにすることも重要ですが、赤ちゃんが乳児用ミルク飲む際の環境が清潔なものであることも重要です。しかし、水が貴重なものとなる被災地では、清潔な哺乳瓶を用意することは困難になります。そこで、清潔な哺乳瓶が準備できない状況でも、赤ちゃんに安全に乳児用ミルクを飲んでもらい、赤ちゃんの命を守るための大切な技術として、「カップ授乳」と呼ばれる、紙コップや湯のみで授乳する方法があります。産婦人科医師有志が被災地に届けた救援物資の中に、カップ授乳の方法を記した紙を入れてもらうことで、この情報を被災地の赤ちゃんと女性に届けることができました。
乳児栄養についての悩みは、当事者である赤ちゃんや女性にとっては常に存在するものではありますが、多くの医療従事者にとっては、災害時などの切羽詰まったタイミングでなければ気付きにくいニッチな悩みごとでもあります。そのような悩みが存在すると気付いた者の責務だと思って,私は情報発信を続けています。それが産婦人科医師の仕事かどうかは、いまだに私の頭の中でも答えは出ていません。ですが、このような情報発信をすることで楽になったり幸せになったり人がいて、そしてそのことを伝えようとしている人があまりいないのであれば、やはりこれは気付いた者の重要なミッションだと思い、情報発信を続けています。
こうしたことを続けてきたモチベーションの中には、科学・医学・支援経験とは別の世界もあります。それは、子どもの頃からの私のヒーローだったアニメキャラクターの声をあてた役者さんとの出会いです。その人とはTwitter(現X)で出会いました。彼は、赤ちゃんを守る情報をいつもリツイートしてくれていました。この応援は私にとってとても大きいものでした。私のブログの読者層、が一気に広がるきっかけになったからです。
後に、その人は講演でおっしゃっていました。5歳の時に、乳飲み子だった弟を空襲から逃がすことはできたものの、弟はその後、栄養失調で亡くなってしまったのだと。母乳や栄養が足りないせいで、子どもが不健康になったり亡くなったりするような世界はあってはならない。この信念を、私はこの人からも受け取りました。
Webインタビュー(後編)
「医師のための乳児栄養Q&A」Webインタビュー(後編)
Q3.本書で先生が強調されているのが、「情報リテラシー」の重要性です。乳児栄養という分野において、「情報リテラシー」が重要なのは何故なのでしょうか。
リテラシーとは文字(Letter)を語源とした言葉で、日本語でいう「読み書きそろばん」とほぼ同義です。1989年の米国大学図書館協会での定義では、「情報が必要なときにそれを認識し、必要な情報を効果的に見つけ出し、評価し、利用する事が出来るように個々人が身につけるべき一連の能力」とされています。この情報リテラシーのうち、健康に繋がるものをヘルスリテラシーと呼ぶこともあります。ヘルスリテラシーは,自身が健康であるための行動を決める根っこの力になります。
今,ほとんどの育児中の女性はスマートフォンをもって、検索機能を使ったり、何かしらのSNSを利用したりして情報を得ています。インターネットの検索機能では、企業等による努力(金銭的な投資も含めて)によって特定の内容を検索結果の上位に表示されやすいように操作できるといった、情報リテラシーの基礎的な事実を学ぶ機会はほとんどありません。
そのため、検索結果の上位に示されている情報や、SNSで沢山の人が「いいね」を押している情報が正しいはずだと思って育児をしていくことになります。
本書の中でも解説している通り、人が妥当な情報をもとに行動を決めることは、正しい地図をもって新しい土地に行くことに例えられます。楽な乳児栄養という目的地にたどり着くためには、正確な地図、即ち妥当な情報が必要です。
検索結果の上位に示されている情報は、必ずしも妥当なものであるとは限りません。ですが多くの女性は困ったときに、解決に至りにくい方法を選んでしまっています。お産前後の女性たちが頼りにしている、身近にいる国家資格をもった医師や助産師、看護師なども、インターネットの検索により専門外の情報を集めるときは、同様の反応をしている可能性があります。
そのため本書では、インターネット上の情報でよくみられる乳児栄養に関する情報がどの程度確かで、どの程度不確かであるかに関する解説も、ほとんどの質問に添えました。
Q4.本書では、医療従事者の善意からの行動が、乳児栄養に関する悩みを生み出してしまっている、ということを指摘されています。改めて、どのような行動がどのような悩みを生み出してしまうのかを教えてください。
まず、ここでいう「悩み」とは、多くの医療従事者はそこに問題があるのだと気づいてすらいなくて、「ないことになっている『悩み』」なのだろうと思っています。
母乳の量を過不足なくするためには、乳汁生成2期の過ごし方に細心の注意を払うことが必要です。日本では、お産後に入院している周産期施設でこの時期を過ごす人が多いでしょう。
この時期の過ごし方に関する適切なケアのシステムが、本書でも紹介したWHO/UNICEFの「母乳育児がうまくいくための10のステップ(2018年改定)」です。この時期をストレスなく過ごすためには、それぞれの周産期施設がお産すぐから赤ちゃんと触れあうことをどう考えているかに注目する必要がありそうです。
たとえば、地元のクリニックでお産をして、産後の夜は新生児室に赤ちゃんを預けようと思っていた女性が、母体搬送などにより別の施設で産後を過ごすことになればどうでしょう。その施設が10のステップによるケアをしていれば、その女性は産後にいきなり赤ちゃんと母子同室をすることになり、ストレスを感じる可能性があります。
反対に、産後すぐから赤ちゃんに触れたいと考えている女性もいます。とはいえ、産後に「自分なんかが,こんなに儚い壊れそうな赤ちゃんを触ってもいいのか?」と不安に思うこともあるでしょう。そんなときに、「今日は赤ちゃんを預けて休みますよね?」と助産師・看護師に言われれば、「そうか、私は赤ちゃんと側にいるのにふさわしくないのか」と考えてしまう人は多くいます。その結果として、赤ちゃんに触りたい、赤ちゃんと一緒にいたいと声に出して伝えるのをためらいがちになります。
母子同室をしなくていい、と医療スタッフが提案するのは、疲れている女性を労りたいという善意によるものでしょう。ですがその提案を受けた女性の中には、母乳育児をしたいと考えていたり、母乳育児のためには産後すぐから授乳をしたほうがよいと知っていたりする人もいます。そして、そのような女性であっても、専門家である助産師や看護師が、自分は赤ちゃんと一緒にいない方が安全であると指導されているように感じて、従う方がいいのだろうと考えるようになることがあるのです。
自信をもてないままに母親としての生活を始めることは、その後の生活にも影響します。 この例のように、妥当な知識や支援技術を背景にもたないケアや声かけは、どんなに善意から行われていても、悩みを生み出すことがあります。母子医療保健従事者が、女性たちの自己効力感も意識して産前・産後の女性たちに接するのは、重要なケアの一部であるはずです。
Q5.本書は主に医療従事者の方に読んでいただくことを念頭に置いてご執筆いただいています。ですが有難いことに、当事者である妊娠・出産を控えている女性の方々、現在まさに赤ちゃんを育てている女性の方々にも読んでいただいているようです。そのような方々に、改めて伝えたいことはありますか?
現在、赤ちゃんを大切に思いながら育てているあなたには、あなたのままで大丈夫!だと伝えたいです。
乳児栄養について,この本でもお示しした「母乳育児がうまくいくための10のステップ」のようしたくて、産婦人科のスタッフに勇気を振りしぼって「こうしたいです」と伝えることがあるかもしれません。「素晴らしいですね!」とスタッフみんなに大切に見守られていく施設でお産できることもあります。
ところが、色々な事情から「あなたのために」という理由で断られることもあります。それは決して、あなたの伝え方や、伝えた内容が間違っているのではありません。
その時のあなたとあなたの赤ちゃんの健康の問題が原因なこともあります。また、「母乳育児がうまくいくための10のステップ」をスタッフが理解していないことが根本にある場合もあります。
健康や体の事情が原因だとしても、あなたが頑張って提案したことを,あなたのためという理由で断わられたとしても、あなたはちっとも悪くないのです。
悪くないとは言っても,母乳育児を希望した気持ちが宙に浮いて戸惑うかも知れません。そんな時には、この本の第3章を読んでみてください。ここでは母乳を出し続けるため、母乳を減らさないための方法を色々とお伝えしています。そのうちの1つだけでもあきらめず続けていれば,母乳をあげ続けることが簡単になります。1滴の母乳を飲ませることができれば母乳育児は成立します。また、1日多く母乳をあげられれば、1日分の母乳育児の利点を赤ちゃんと自分に届けることができます。
混合栄養については、この本に書かれた情報は今ひとつ頼りないと思った人もいらっしゃるかもしれません。本書では、乳児栄養のグローバルスタンダードである母乳育児を続けるためにも、母乳が止まらないようにする方法を中心にお示ししました。
実は混合栄養については、誰にでも通じる科学的根拠の示されたお手本になるような方法がありません。混合栄養は一組一組の親子が築き上げていく栄養のかたちだからです。つまり、本来ならば専門家からのケアが最も必要になる乳児栄養の形であるともいえます。
お値段の安くはないこの医学書を読んで、わが子の育児に活かそうとした熱意に敬意を送ります。折角お求めになった本です。どれか1つだけでもお役に立てる事を願っております。
Q6.最後に、本書を読まれた方、これから読まれる方へのメッセージをお願いします。
紙の本の表紙にいる女性と赤ちゃんは、淡々と質問を伝える母子の姿です。テーブルの上にはお気に入りのお茶やケーキが描かれてます。そのカバーを外してご覧になってみてください。違う表情が隠れています。
この本を手に取った医師・助産師・保健師・看護師・歯科医・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・研修医・医学部学生など医療の専門家と、赤ちゃんを育てる女性とその家族の皆さま、職場の皆さまが、この本によって1つでも2つでも笑顔を増やしていただけましたら幸いです。
Q3.本書で先生が強調されているのが、「情報リテラシー」の重要性です。乳児栄養という分野において、「情報リテラシー」が重要なのは何故なのでしょうか。
リテラシーとは文字(Letter)を語源とした言葉で、日本語でいう「読み書きそろばん」とほぼ同義です。1989年の米国大学図書館協会での定義では、「情報が必要なときにそれを認識し、必要な情報を効果的に見つけ出し、評価し、利用する事が出来るように個々人が身につけるべき一連の能力」とされています。この情報リテラシーのうち、健康に繋がるものをヘルスリテラシーと呼ぶこともあります。ヘルスリテラシーは,自身が健康であるための行動を決める根っこの力になります。
今,ほとんどの育児中の女性はスマートフォンをもって、検索機能を使ったり、何かしらのSNSを利用したりして情報を得ています。インターネットの検索機能では、企業等による努力(金銭的な投資も含めて)によって特定の内容を検索結果の上位に表示されやすいように操作できるといった、情報リテラシーの基礎的な事実を学ぶ機会はほとんどありません。
そのため、検索結果の上位に示されている情報や、SNSで沢山の人が「いいね」を押している情報が正しいはずだと思って育児をしていくことになります。
本書の中でも解説している通り、人が妥当な情報をもとに行動を決めることは、正しい地図をもって新しい土地に行くことに例えられます。楽な乳児栄養という目的地にたどり着くためには、正確な地図、即ち妥当な情報が必要です。
検索結果の上位に示されている情報は、必ずしも妥当なものであるとは限りません。ですが多くの女性は困ったときに、解決に至りにくい方法を選んでしまっています。お産前後の女性たちが頼りにしている、身近にいる国家資格をもった医師や助産師、看護師なども、インターネットの検索により専門外の情報を集めるときは、同様の反応をしている可能性があります。
そのため本書では、インターネット上の情報でよくみられる乳児栄養に関する情報がどの程度確かで、どの程度不確かであるかに関する解説も、ほとんどの質問に添えました。
Q4.本書では、医療従事者の善意からの行動が、乳児栄養に関する悩みを生み出してしまっている、ということを指摘されています。改めて、どのような行動がどのような悩みを生み出してしまうのかを教えてください。
まず、ここでいう「悩み」とは、多くの医療従事者はそこに問題があるのだと気づいてすらいなくて、「ないことになっている『悩み』」なのだろうと思っています。
母乳の量を過不足なくするためには、乳汁生成2期の過ごし方に細心の注意を払うことが必要です。日本では、お産後に入院している周産期施設でこの時期を過ごす人が多いでしょう。
この時期の過ごし方に関する適切なケアのシステムが、本書でも紹介したWHO/UNICEFの「母乳育児がうまくいくための10のステップ(2018年改定)」です。この時期をストレスなく過ごすためには、それぞれの周産期施設がお産すぐから赤ちゃんと触れあうことをどう考えているかに注目する必要がありそうです。
たとえば、地元のクリニックでお産をして、産後の夜は新生児室に赤ちゃんを預けようと思っていた女性が、母体搬送などにより別の施設で産後を過ごすことになればどうでしょう。その施設が10のステップによるケアをしていれば、その女性は産後にいきなり赤ちゃんと母子同室をすることになり、ストレスを感じる可能性があります。
反対に、産後すぐから赤ちゃんに触れたいと考えている女性もいます。とはいえ、産後に「自分なんかが,こんなに儚い壊れそうな赤ちゃんを触ってもいいのか?」と不安に思うこともあるでしょう。そんなときに、「今日は赤ちゃんを預けて休みますよね?」と助産師・看護師に言われれば、「そうか、私は赤ちゃんと側にいるのにふさわしくないのか」と考えてしまう人は多くいます。その結果として、赤ちゃんに触りたい、赤ちゃんと一緒にいたいと声に出して伝えるのをためらいがちになります。
母子同室をしなくていい、と医療スタッフが提案するのは、疲れている女性を労りたいという善意によるものでしょう。ですがその提案を受けた女性の中には、母乳育児をしたいと考えていたり、母乳育児のためには産後すぐから授乳をしたほうがよいと知っていたりする人もいます。そして、そのような女性であっても、専門家である助産師や看護師が、自分は赤ちゃんと一緒にいない方が安全であると指導されているように感じて、従う方がいいのだろうと考えるようになることがあるのです。
自信をもてないままに母親としての生活を始めることは、その後の生活にも影響します。 この例のように、妥当な知識や支援技術を背景にもたないケアや声かけは、どんなに善意から行われていても、悩みを生み出すことがあります。母子医療保健従事者が、女性たちの自己効力感も意識して産前・産後の女性たちに接するのは、重要なケアの一部であるはずです。
Q5.本書は主に医療従事者の方に読んでいただくことを念頭に置いてご執筆いただいています。ですが有難いことに、当事者である妊娠・出産を控えている女性の方々、現在まさに赤ちゃんを育てている女性の方々にも読んでいただいているようです。そのような方々に、改めて伝えたいことはありますか?
現在、赤ちゃんを大切に思いながら育てているあなたには、あなたのままで大丈夫!だと伝えたいです。
乳児栄養について,この本でもお示しした「母乳育児がうまくいくための10のステップ」のようしたくて、産婦人科のスタッフに勇気を振りしぼって「こうしたいです」と伝えることがあるかもしれません。「素晴らしいですね!」とスタッフみんなに大切に見守られていく施設でお産できることもあります。
ところが、色々な事情から「あなたのために」という理由で断られることもあります。それは決して、あなたの伝え方や、伝えた内容が間違っているのではありません。
その時のあなたとあなたの赤ちゃんの健康の問題が原因なこともあります。また、「母乳育児がうまくいくための10のステップ」をスタッフが理解していないことが根本にある場合もあります。
健康や体の事情が原因だとしても、あなたが頑張って提案したことを,あなたのためという理由で断わられたとしても、あなたはちっとも悪くないのです。
悪くないとは言っても,母乳育児を希望した気持ちが宙に浮いて戸惑うかも知れません。そんな時には、この本の第3章を読んでみてください。ここでは母乳を出し続けるため、母乳を減らさないための方法を色々とお伝えしています。そのうちの1つだけでもあきらめず続けていれば,母乳をあげ続けることが簡単になります。1滴の母乳を飲ませることができれば母乳育児は成立します。また、1日多く母乳をあげられれば、1日分の母乳育児の利点を赤ちゃんと自分に届けることができます。
混合栄養については、この本に書かれた情報は今ひとつ頼りないと思った人もいらっしゃるかもしれません。本書では、乳児栄養のグローバルスタンダードである母乳育児を続けるためにも、母乳が止まらないようにする方法を中心にお示ししました。
実は混合栄養については、誰にでも通じる科学的根拠の示されたお手本になるような方法がありません。混合栄養は一組一組の親子が築き上げていく栄養のかたちだからです。つまり、本来ならば専門家からのケアが最も必要になる乳児栄養の形であるともいえます。
お値段の安くはないこの医学書を読んで、わが子の育児に活かそうとした熱意に敬意を送ります。折角お求めになった本です。どれか1つだけでもお役に立てる事を願っております。
Q6.最後に、本書を読まれた方、これから読まれる方へのメッセージをお願いします。
紙の本の表紙にいる女性と赤ちゃんは、淡々と質問を伝える母子の姿です。テーブルの上にはお気に入りのお茶やケーキが描かれてます。そのカバーを外してご覧になってみてください。違う表情が隠れています。
この本を手に取った医師・助産師・保健師・看護師・歯科医・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・研修医・医学部学生など医療の専門家と、赤ちゃんを育てる女性とその家族の皆さま、職場の皆さまが、この本によって1つでも2つでも笑顔を増やしていただけましたら幸いです。