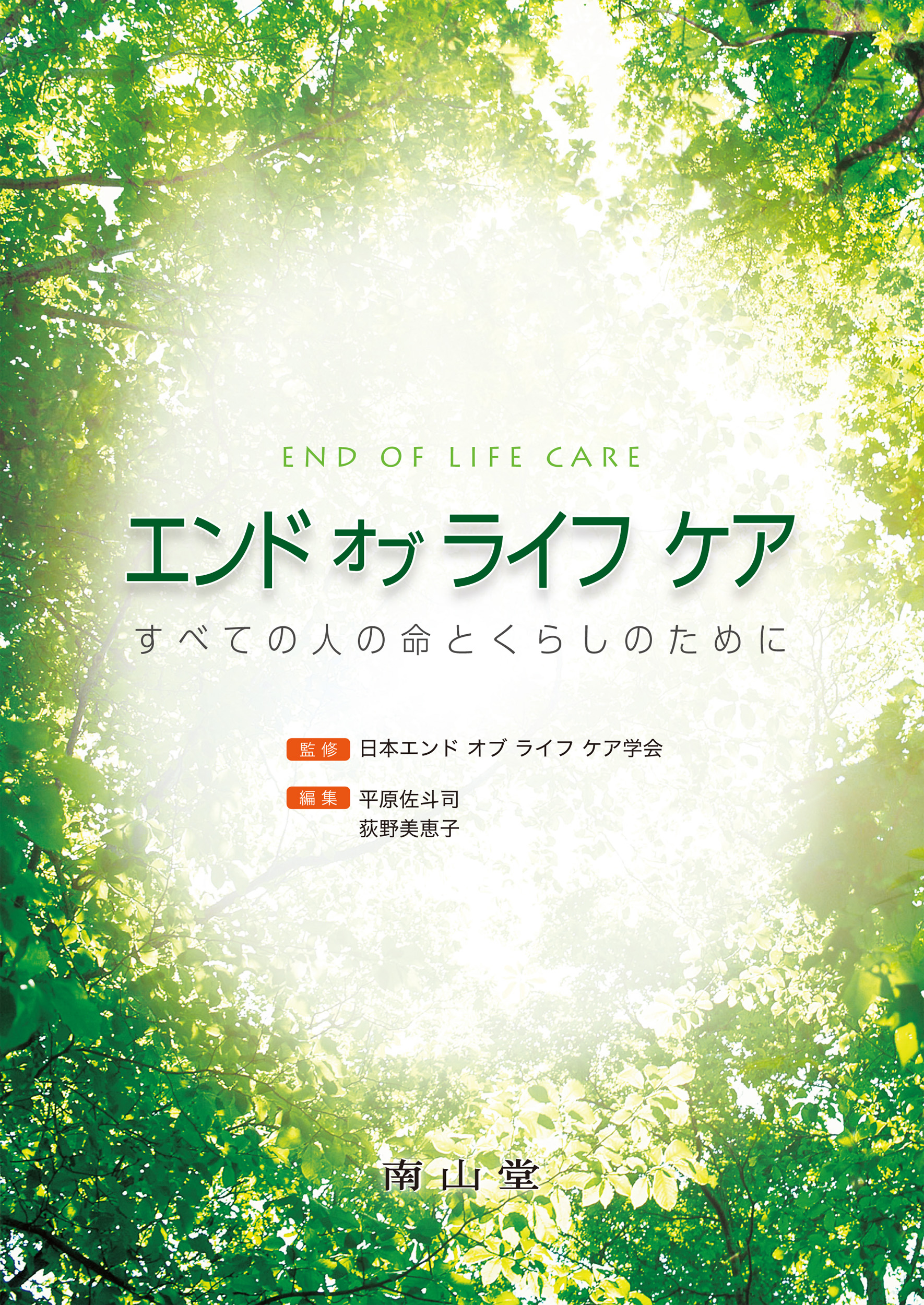死別と悲嘆の精神医学
1版
名古屋市立大学大学院医学研究科精神・認知・行動医学分野 教授 明智龍男 編
帝京大学薬学部薬学教育推進センター 教授 浅井真理子 編
関西学院大学人間福祉学部人間科学科 教授 坂口幸弘 編
兵庫県こころのケアセンター研究部 上席研究主幹 瀬藤乃理子 編
国立がん研究センター中央病院 精神腫瘍科科長 松岡弘道 編
定価
4,400円(本体 4,000円 +税10%)
- B5判 285頁
- 2025年4月 発行
- ISBN 978-4-525-38261-2
本邦初、死別と悲嘆に関する本格テキストブック
近年,ICD-11において「遷延性悲嘆症」が疾患として位置づけられたことに象徴されるように,医療が死別による苦しみに適切に関わることへの関心が高まっています.わが国においても,2022年に「遺族ケアガイドライン」が策定され,医療従事者が遺族ケアに関わるための道筋が示されました.
本書は,死別と悲嘆に関して精神医学的・心理学的な視点から取り上げる本邦初の書籍として,その概念から治療・ケアの実際,事例までを網羅的に解説しました.診断基準や国内外のガイドラインはもちろんのこと、死別と悲嘆に関してこれまでに蓄積されてきた数多くのエビデンスを紹介しています.遺族を支えたいと願うすべての医療福祉従事者に必要な知識が網羅された一冊です.
- 序文
- 目次
序文
発刊によせて
死別は多くの人が経験する人生最大の苦悩である.医療の世界においては,病で亡くなっていかれる人に焦点を当てられることが多いが,死別を経験するということは遺族にとって死別の苦しみの中で生きてゆくことの始まりを意味する.その道は険しく,ある人は年余にわたる時間を経過してようやく患者の死を受け容れ,行きつ戻りつしながら新しい生活に適応していく.ある人は専門家の治療やケアが望まれる状態を経験する.
近親者の死を代表とする喪失によってもたらされる様々な反応を包含した概念をグリーフというが,一般的には深い悲しみや苦悩などのこころの状態に焦点をあてられることが多い.一方で,死別は遺族の考え方や価値観のみならず身体的な健康にも影響を及ぼし,時として自死という悲痛な結末に関連する.
私自身は精神科医であるが,例えばなかなか改善がみられないうつ状態の患者さんを拝見するなかで,死別という観点から患者さんを診る視点が乏しかったことを反省する日々が続いている.死別の苦しみを患者さん自らが語らないことも多いからであるが,ヒトのこころを最も大切にすべき医学の領域にいながら,それをできていないと感じた際には,自身の医師としての底の浅さを垣間見たような気持ちになり,やりきれなくもなった.ヒトが死別について語らないのは,それだけ傷ついていることを意味しているようにも思うが,その苦しみや悲しみを掬い取れていないとき,患者さんの苦痛はより深いものになってしまうのかもしれない.そういう経験を重ねる中で,死別や悲嘆を精神医学という学問の観点からきちんと俯瞰し,現時点でできること,できないこと,すべきでないこと,今後の課題などを整理する必要を感じた.
おそらく医学の領域の中で死別を真正面から扱うのは精神医学およびその関連領域のみではないだろうか.一方,精神医学の世界においても死別後の精神状態に関して,歴史的にみてもその診断概念すら右往左往しているのが現状である.どこまでが正常でどういった状態になると医療が必要になるのか.明確な線引きはできないかもしれないが,その概念や現時点での治療やケアに関するエビデンスそして問題点について自覚的でありたいと思う.
超高齢社会を迎えた現在のわが国は多死社会とも言われており,その多くが疾病罹患による死である.わが国は先進国の中ではとびぬけて自死も多く,そのほとんどの背景にはこころの病が関連することもよく知られた事実である.文化に影響を受けることも多い悲嘆を過度に医療化することは厳に慎みたいと思うが,一方,もっと医療が関与すべき死別に関連する諸問題もあるのかもしれない.
様々なことを一臨床医として考える中,厚労省科学研究費補助金の研究班で,家族・遺族ケアの現状を明らかにする研究班の主任研究者をつとめることになり,その結果として,日本サイコオンコロジー学会で遺族ケアガイドラインを策定する機会を得た.そのプロセスで,死別にまつわる医学的な知見はまだまだ乏しく,未整理の領域も大変多いこと,そしてそれゆえ医療の周辺にある諸問題に気づくことができておらず,ひいてはきちんとケアや治療が提供できていないことを知った.
本書を編む一つの契機になったのが,2023 年に開催された日本精神神経学会総会での「死別の精神医学」というシンポジウムであり,その際に南山堂の方に声をかけていただいたことに端を発する.また同学会で精神腫瘍学のシンポジウムが行われた際に,ご家族をがんで失われた患者会の代表の方が,グリーフケアの大切さを強くお話され,学会としてもぜひその必要性を広く伝えてほしいと発言されていた.これらも後押しすることに
なった.
自身のことで恐縮であるが,自分自身にとっての未消化の経験として,本書の中にも紹介されている「記者からみた死別 ─ 続「未完の論文」」に登場されている故・H 先生のことがある.H 先生は,前立腺がんの患者さんであり,私が勤めている大学の文系学部の教員でもあったことから,私も診療チームに参加させていただいた.こころを病んだ奥様がお子さんを殺害し,その後,奥様ご本人も自死を遂げられた.H 先生は筆舌に尽くしがたい悲しみと苦しみの中でご自身のがんの進行を経験しながらも,大学教員としての仕事を懸命にこなしておられ,最後にがんで亡くなられた.H 先生に自分が十分な援助ができていたのかを振り返ると今でも胸が痛くなる.そして,この経験は,今でも私自身の頭から離れず,ことあるごとに思い出されるが,これ自体が私自身の今でも続く悲嘆なのではないかと思う.
人は生きている中で,好むと好まざるとにかかわらず,つらい死別や悲嘆を経験する.災害で家族を失ったり,犯罪被害で大切な人を失う方もいる.死産で苦しむ方もいる.人は時としてそんな中でも生きていかなくてはならない.精神医学をはじめとする学問はそういった方々にとってきちんと意味ある役割を果たせているのだろうか.医療の本質が医学の社会的な適応であるとしたら,精神医学は死別や悲嘆にまつわるヒトの苦しみを過度
に医療化することなく,しかし,関与すべき点についてはもっと積極的であってもよいのかもしれないと感じる.
本書は,そういったことに悩んでいる医療者の助けになることを願い,死別や悲嘆に関する精神医学を中心とする諸領域に関して第一線で活躍されている先生方に筆をとっていただいた.
2025 年4 月
名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野
明智龍男
死別は多くの人が経験する人生最大の苦悩である.医療の世界においては,病で亡くなっていかれる人に焦点を当てられることが多いが,死別を経験するということは遺族にとって死別の苦しみの中で生きてゆくことの始まりを意味する.その道は険しく,ある人は年余にわたる時間を経過してようやく患者の死を受け容れ,行きつ戻りつしながら新しい生活に適応していく.ある人は専門家の治療やケアが望まれる状態を経験する.
近親者の死を代表とする喪失によってもたらされる様々な反応を包含した概念をグリーフというが,一般的には深い悲しみや苦悩などのこころの状態に焦点をあてられることが多い.一方で,死別は遺族の考え方や価値観のみならず身体的な健康にも影響を及ぼし,時として自死という悲痛な結末に関連する.
私自身は精神科医であるが,例えばなかなか改善がみられないうつ状態の患者さんを拝見するなかで,死別という観点から患者さんを診る視点が乏しかったことを反省する日々が続いている.死別の苦しみを患者さん自らが語らないことも多いからであるが,ヒトのこころを最も大切にすべき医学の領域にいながら,それをできていないと感じた際には,自身の医師としての底の浅さを垣間見たような気持ちになり,やりきれなくもなった.ヒトが死別について語らないのは,それだけ傷ついていることを意味しているようにも思うが,その苦しみや悲しみを掬い取れていないとき,患者さんの苦痛はより深いものになってしまうのかもしれない.そういう経験を重ねる中で,死別や悲嘆を精神医学という学問の観点からきちんと俯瞰し,現時点でできること,できないこと,すべきでないこと,今後の課題などを整理する必要を感じた.
おそらく医学の領域の中で死別を真正面から扱うのは精神医学およびその関連領域のみではないだろうか.一方,精神医学の世界においても死別後の精神状態に関して,歴史的にみてもその診断概念すら右往左往しているのが現状である.どこまでが正常でどういった状態になると医療が必要になるのか.明確な線引きはできないかもしれないが,その概念や現時点での治療やケアに関するエビデンスそして問題点について自覚的でありたいと思う.
超高齢社会を迎えた現在のわが国は多死社会とも言われており,その多くが疾病罹患による死である.わが国は先進国の中ではとびぬけて自死も多く,そのほとんどの背景にはこころの病が関連することもよく知られた事実である.文化に影響を受けることも多い悲嘆を過度に医療化することは厳に慎みたいと思うが,一方,もっと医療が関与すべき死別に関連する諸問題もあるのかもしれない.
様々なことを一臨床医として考える中,厚労省科学研究費補助金の研究班で,家族・遺族ケアの現状を明らかにする研究班の主任研究者をつとめることになり,その結果として,日本サイコオンコロジー学会で遺族ケアガイドラインを策定する機会を得た.そのプロセスで,死別にまつわる医学的な知見はまだまだ乏しく,未整理の領域も大変多いこと,そしてそれゆえ医療の周辺にある諸問題に気づくことができておらず,ひいてはきちんとケアや治療が提供できていないことを知った.
本書を編む一つの契機になったのが,2023 年に開催された日本精神神経学会総会での「死別の精神医学」というシンポジウムであり,その際に南山堂の方に声をかけていただいたことに端を発する.また同学会で精神腫瘍学のシンポジウムが行われた際に,ご家族をがんで失われた患者会の代表の方が,グリーフケアの大切さを強くお話され,学会としてもぜひその必要性を広く伝えてほしいと発言されていた.これらも後押しすることに
なった.
自身のことで恐縮であるが,自分自身にとっての未消化の経験として,本書の中にも紹介されている「記者からみた死別 ─ 続「未完の論文」」に登場されている故・H 先生のことがある.H 先生は,前立腺がんの患者さんであり,私が勤めている大学の文系学部の教員でもあったことから,私も診療チームに参加させていただいた.こころを病んだ奥様がお子さんを殺害し,その後,奥様ご本人も自死を遂げられた.H 先生は筆舌に尽くしがたい悲しみと苦しみの中でご自身のがんの進行を経験しながらも,大学教員としての仕事を懸命にこなしておられ,最後にがんで亡くなられた.H 先生に自分が十分な援助ができていたのかを振り返ると今でも胸が痛くなる.そして,この経験は,今でも私自身の頭から離れず,ことあるごとに思い出されるが,これ自体が私自身の今でも続く悲嘆なのではないかと思う.
人は生きている中で,好むと好まざるとにかかわらず,つらい死別や悲嘆を経験する.災害で家族を失ったり,犯罪被害で大切な人を失う方もいる.死産で苦しむ方もいる.人は時としてそんな中でも生きていかなくてはならない.精神医学をはじめとする学問はそういった方々にとってきちんと意味ある役割を果たせているのだろうか.医療の本質が医学の社会的な適応であるとしたら,精神医学は死別や悲嘆にまつわるヒトの苦しみを過度
に医療化することなく,しかし,関与すべき点についてはもっと積極的であってもよいのかもしれないと感じる.
本書は,そういったことに悩んでいる医療者の助けになることを願い,死別や悲嘆に関する精神医学を中心とする諸領域に関して第一線で活躍されている先生方に筆をとっていただいた.
2025 年4 月
名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野
明智龍男
目次
Ⅰ 悲嘆の理論と概念
1 悲嘆の精神医学の歴史
2 悲嘆心理学の歴史的展開
3 悲嘆の概念と実態
4 悲嘆の概念と関連要因
5 悲嘆への対応
6 悲嘆について学ぶ
Column 遺族ケアへの期待
Column 哀しみの個別性のなかにこそ
Ⅱ 悲嘆の診断とアセスメント
1 精神医学と悲嘆の歴史
2 遺族が示すさまざまな症状
3 心療内科と悲嘆
4 生前の家族のリスクアセスメント
5 治療が必要な遺族に対するアセスメント・ツール
Column 膵臓がん遺族の悲しみと遺族ケアの重要性
Column 死別や悲嘆を調査するときに
Ⅲ 悲嘆の治療とケア
1 遺族ケアガイドライン
2 薬物療法のエビデンス
3 心理療法のエビデンス
4 海外の遺族ケアガイドライン
5 行動活性化療法
6 対人関係療法
7 セルフコンパッション
8 生きる意味に焦点を当てた精神療法
9 遷延性悲嘆治療
10 遺族の心的外傷後成長
Column グリーフから希望を
Column 脳科学と悲嘆
Ⅳ 遺族支援の実践
A 実践編
1 悲嘆支援のエッセンス ―すべきこと・すべきでないこと―
2 トラウマと悲嘆
3 患者を亡くしたスタッフへのグリーフケア
4 悲嘆とナラティヴ
5 主治医・看護師等の非精神・心理専門職が行うグリーフケア
6 医師と心理職の連携
7 遺族外来の試み
8 看護職が行うグリーフケア
9 子どもを亡くした親へのグリーフケア
10 親(大切な人)を亡くした子どもへのグリーフケア
Column アルコール依存症とグリーフ
Column 認知症と悲嘆
Column 精神障害者の死別・悲嘆
B さまざまな立場から
1 精神科医・緩和ケア医の立場から
2 心療内科医の立場から
3 がん看護師の立場から
4 精神科看護師の立場から
5 心理士の立場から
6 助産師の立場から
7 遺族会運営の立場から
Column COVID-19 と悲嘆
Column 宗教者との連携
Column グリーフケアにおける心理職の倫理を考える
C 特別な配慮
1 救急における配慮
2 自死遺族支援における配慮
3 事故における配慮
4 災害における配慮
Column コミュニティベースの遺族ケア・グリーフケア
Column 彼が生きた意味―続・未完の論文
巻末資料
索 引
1 悲嘆の精神医学の歴史
2 悲嘆心理学の歴史的展開
3 悲嘆の概念と実態
4 悲嘆の概念と関連要因
5 悲嘆への対応
6 悲嘆について学ぶ
Column 遺族ケアへの期待
Column 哀しみの個別性のなかにこそ
Ⅱ 悲嘆の診断とアセスメント
1 精神医学と悲嘆の歴史
2 遺族が示すさまざまな症状
3 心療内科と悲嘆
4 生前の家族のリスクアセスメント
5 治療が必要な遺族に対するアセスメント・ツール
Column 膵臓がん遺族の悲しみと遺族ケアの重要性
Column 死別や悲嘆を調査するときに
Ⅲ 悲嘆の治療とケア
1 遺族ケアガイドライン
2 薬物療法のエビデンス
3 心理療法のエビデンス
4 海外の遺族ケアガイドライン
5 行動活性化療法
6 対人関係療法
7 セルフコンパッション
8 生きる意味に焦点を当てた精神療法
9 遷延性悲嘆治療
10 遺族の心的外傷後成長
Column グリーフから希望を
Column 脳科学と悲嘆
Ⅳ 遺族支援の実践
A 実践編
1 悲嘆支援のエッセンス ―すべきこと・すべきでないこと―
2 トラウマと悲嘆
3 患者を亡くしたスタッフへのグリーフケア
4 悲嘆とナラティヴ
5 主治医・看護師等の非精神・心理専門職が行うグリーフケア
6 医師と心理職の連携
7 遺族外来の試み
8 看護職が行うグリーフケア
9 子どもを亡くした親へのグリーフケア
10 親(大切な人)を亡くした子どもへのグリーフケア
Column アルコール依存症とグリーフ
Column 認知症と悲嘆
Column 精神障害者の死別・悲嘆
B さまざまな立場から
1 精神科医・緩和ケア医の立場から
2 心療内科医の立場から
3 がん看護師の立場から
4 精神科看護師の立場から
5 心理士の立場から
6 助産師の立場から
7 遺族会運営の立場から
Column COVID-19 と悲嘆
Column 宗教者との連携
Column グリーフケアにおける心理職の倫理を考える
C 特別な配慮
1 救急における配慮
2 自死遺族支援における配慮
3 事故における配慮
4 災害における配慮
Column コミュニティベースの遺族ケア・グリーフケア
Column 彼が生きた意味―続・未完の論文
巻末資料
索 引