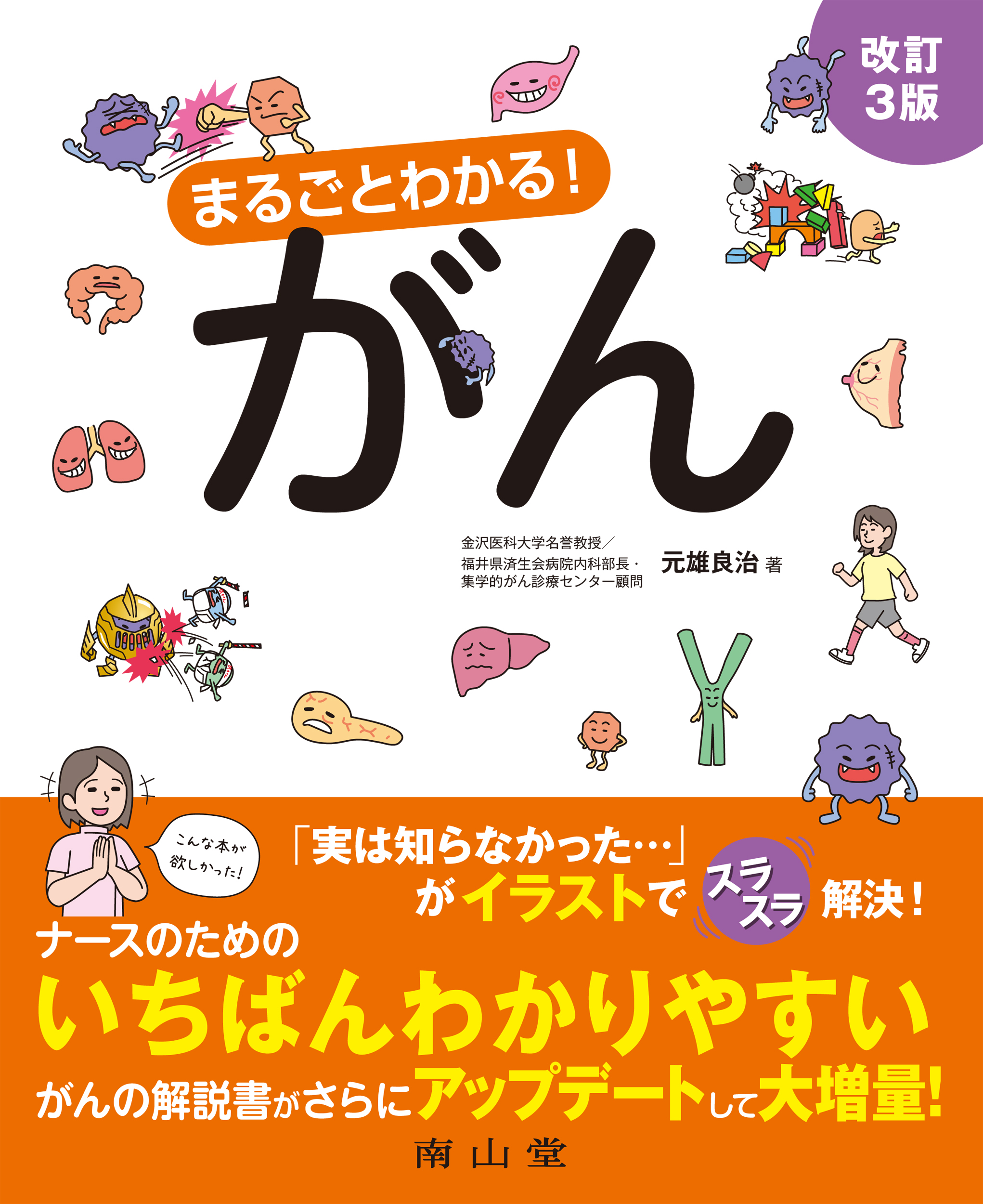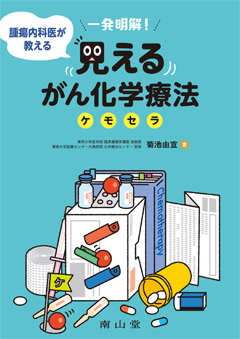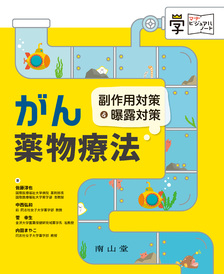図解 腫瘍薬学
改訂2版
鈴鹿医療科学大学薬学部 客員教授 川西正祐 編
静岡県立大学薬学部 教授 賀川義之 編
鈴鹿医療科学大学薬学部 教授 大井一弥 編
定価
5,940円(本体 5,400円 +税10%)
- B5判 555頁
- 2025年3月 発行
- ISBN 978-4-525-72162-6
薬学的視点でがんに関わる「腫瘍薬学」のすべてをこの一冊に!
本書は,がんの発生,予防,抗がん,緩和医療といったがん薬物療法に関連する内容を,豊富な図表とともに解説しています.今回の改訂では,さらに使いやすい教科書を目指し,薬学教育モデル・コア・カリキュラム令和4年度改訂版に準拠した情報の更新ほか解説レベルの見直しなどを行いました.
- 序文
- 目次
序文
改訂2版の序
わが国は超高齢社会になり,年々がんの発症率が高まっている.2023 年のがんによる死亡者数は約38 万人であり,死亡総数に占める割合は24.3%で,心疾患14.7%と脳血管疾患6.6%を合わせた循環器疾患の割合よりも多い.また,循環器疾患による死亡数は男女でほとんど変わらないが,がんについては男性が女性に比べて約1.4 倍多く,結果として,男性は女性に比べて平均寿命が短い.現在,およそ2 人に1 人ががんに罹患し,4 人に1 人ががんで死亡している.がんは,国民にとって最大の健康上の課題である.
がんは生活習慣病の一つで,食習慣,運動不足,喫煙,飲酒,肥満などに起因している.がん細胞は,自立増殖能を有し,発生部位から増殖・浸潤し,さらに転移することがある.進行度によっては,がん悪液質を経て死亡することが多い.近年,がん治療では手術療法,放射線療法,薬物療法に免疫療法を加えた集学的な治療が行われている.がん薬物療法として,化学療法に用いられる細胞障害性抗がん薬に加えて画期的な分子標的薬が続々と開発されている.免疫チェックポイント阻害薬は分子標的薬でもあるが,重要な免疫療法の一つでもある.
薬学教育の分野には,がんに関連する専門教科が多い.生体が発がん因子に曝露されて,標的である遺伝子(DNA)に変異をもたらす発がん機構に基づいて,がん予防に関与する「衛生薬学」がある.次いで,がん生物学,特にがん細胞の増殖・浸潤やシグナル伝達を研究する「生物系薬学」がある.さらに,抗がん薬の薬理から治療法を探求する「薬物治療学」を含む「医療薬学」があり,がん患者に対するファーマシューティカル(薬学的)ケアを研究する「臨床薬学」分野もある.しかし,これらの分野は,がんを部分的に扱っており,がんの基礎から臨床まで体系的に編集した教科書はなかった.本書は,「腫瘍薬学」を新しい薬学分野の一つとして位置付けている.腫瘍薬学とは,がん予防に重要な発がんの発症メカニズムおよびがん治療法の作用や副作用の発現メカニズムを,病態と関連付けて薬学的視点から総括する学問であると定義した.本書では,基礎と臨床の知識がシームレスに結びつくよう構成し,最近の情報も盛り込んだ教科書として編纂した.近年,がんは治療だけでなく予防の重要性も増しているため,基礎・臨床の両視点を統合的に学び,薬学的にアプローチすることが重要と考えられる.
なお,「図解 腫瘍薬学」初版は2020 年8 月に刊行されている.初版発刊後のがん研究では,エピジェネティクス(後成遺伝学)とも呼ばれ,DNA の配列変化なしに遺伝子機能が変化する現象を解明する研究が進展し,DNA のメチル化など,エピジェネティックな変化ががん化を引き起こす可能性が示された.今後も新規の診断や治療の開発が期待されている.改訂2 版では,最近のがん研究の成果を踏まえ全面的に書き直し,理解を深めるために内容の多くを図解する方針で編集を進めた.薬学生だけでなく,薬剤師やがん専門薬剤師を目指す方など,がん予防やがん治療に関わるすべての医療従事者に本書をお読みいただければ幸いである.
最後に,本書の編集に多大なご協力をいただいた南山堂編集部の江石遥夏氏,庄司豊隆氏,古川晶彦取締役および関係諸氏に感謝する.
2025 年2 月
編者を代表して 川西 正祐
わが国は超高齢社会になり,年々がんの発症率が高まっている.2023 年のがんによる死亡者数は約38 万人であり,死亡総数に占める割合は24.3%で,心疾患14.7%と脳血管疾患6.6%を合わせた循環器疾患の割合よりも多い.また,循環器疾患による死亡数は男女でほとんど変わらないが,がんについては男性が女性に比べて約1.4 倍多く,結果として,男性は女性に比べて平均寿命が短い.現在,およそ2 人に1 人ががんに罹患し,4 人に1 人ががんで死亡している.がんは,国民にとって最大の健康上の課題である.
がんは生活習慣病の一つで,食習慣,運動不足,喫煙,飲酒,肥満などに起因している.がん細胞は,自立増殖能を有し,発生部位から増殖・浸潤し,さらに転移することがある.進行度によっては,がん悪液質を経て死亡することが多い.近年,がん治療では手術療法,放射線療法,薬物療法に免疫療法を加えた集学的な治療が行われている.がん薬物療法として,化学療法に用いられる細胞障害性抗がん薬に加えて画期的な分子標的薬が続々と開発されている.免疫チェックポイント阻害薬は分子標的薬でもあるが,重要な免疫療法の一つでもある.
薬学教育の分野には,がんに関連する専門教科が多い.生体が発がん因子に曝露されて,標的である遺伝子(DNA)に変異をもたらす発がん機構に基づいて,がん予防に関与する「衛生薬学」がある.次いで,がん生物学,特にがん細胞の増殖・浸潤やシグナル伝達を研究する「生物系薬学」がある.さらに,抗がん薬の薬理から治療法を探求する「薬物治療学」を含む「医療薬学」があり,がん患者に対するファーマシューティカル(薬学的)ケアを研究する「臨床薬学」分野もある.しかし,これらの分野は,がんを部分的に扱っており,がんの基礎から臨床まで体系的に編集した教科書はなかった.本書は,「腫瘍薬学」を新しい薬学分野の一つとして位置付けている.腫瘍薬学とは,がん予防に重要な発がんの発症メカニズムおよびがん治療法の作用や副作用の発現メカニズムを,病態と関連付けて薬学的視点から総括する学問であると定義した.本書では,基礎と臨床の知識がシームレスに結びつくよう構成し,最近の情報も盛り込んだ教科書として編纂した.近年,がんは治療だけでなく予防の重要性も増しているため,基礎・臨床の両視点を統合的に学び,薬学的にアプローチすることが重要と考えられる.
なお,「図解 腫瘍薬学」初版は2020 年8 月に刊行されている.初版発刊後のがん研究では,エピジェネティクス(後成遺伝学)とも呼ばれ,DNA の配列変化なしに遺伝子機能が変化する現象を解明する研究が進展し,DNA のメチル化など,エピジェネティックな変化ががん化を引き起こす可能性が示された.今後も新規の診断や治療の開発が期待されている.改訂2 版では,最近のがん研究の成果を踏まえ全面的に書き直し,理解を深めるために内容の多くを図解する方針で編集を進めた.薬学生だけでなく,薬剤師やがん専門薬剤師を目指す方など,がん予防やがん治療に関わるすべての医療従事者に本書をお読みいただければ幸いである.
最後に,本書の編集に多大なご協力をいただいた南山堂編集部の江石遥夏氏,庄司豊隆氏,古川晶彦取締役および関係諸氏に感謝する.
2025 年2 月
編者を代表して 川西 正祐
目次
1章 がんの分類と疫学
1 腫瘍の分類
1. 腫瘍の定義
2. 組織発生学的分類:上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍
3. 組織型分類:悪性腫瘍の分類
4. 病期分類:TNM 分類と病期分類
2 がん統計の概要
わが国におけるがん死亡と罹患
3 がんの成因
がんのリスク要因
2章 発がん因子と発がん過程
1 化学的因子
1. 多環芳香族炭化水素
2. 芳香族アミノ化合物
3. 有機溶剤
4. 金属
5. 高分子・プラスチックモノマー
6. 高分子添加剤
7. ガス状物質
8. 農薬
9. ダイオキシン類
10. カビ毒(マイコトキシン)
11. ニトロソ化合物
12. 有機フッ素化合物(PFAS)
13. 食用植物
14. 食品添加物
2 生物学的因子
1. 寄生虫
2. 細菌
3. ウイルス
3 物理化学的因子
1. 紫外線
2. 電離放射線
3. 繊維・粒子状物質
4 イニシエーションとプロモーション(多段階発がん)
1. 多段階発がん説
2. プロモーション
3. プログレッション
5 発がん物質の代謝活性化による遺伝子損傷
1. 発がん物質
2. 代謝活性化
3. 代謝活性化された究極発がん物質による遺伝子損傷
6 活性酸素,一酸化窒素による遺伝子損傷
1. 活性酸素種
2. 一酸化窒素
7 遺伝子変異・修復
1. 酵素による直接修復
2. DNA 1 本鎖切断の修復機構
3. DNA 2 本鎖切断の修復機構
4. 損傷乗り越え複製
5. 染色体の異常
8 がん関連遺伝子
がん原遺伝子
9 がんのエピジェネティクス
1. DNA メチル化とは
2. がんにおけるDNA メチル化異常と治療応用
3. ヒストン修飾とは
4. がんにおけるヒストン修飾異常と治療応用
3章 がんの予防
1 一次予防と二次予防
1. がん予防の背景
2. がん予防の分類
3. がん予防の分類と戦略
4. 一次予防の課題と対策
5. 二次予防の課題と対策
2 がんの化学予防物質
3 発がん性リスクアセスメント
1. 発がん性の確認
2. 量- 反応アセスメント
3. 曝露アセスメント
4. リスク判定
4 発がん性物質のスクリーニング法
1. 変異原性試験
2. 染色体異常試験
3. DNA 損傷性試験
4. 遺伝子損傷性のない発がん性物質のスクリーニング法
4章 がんの生物学
1 がんの転移・浸潤
1. 転移のメカニズム
2. 転移と上皮間葉転換
3. 転移の臓器特異性 / 組織向性
上皮間葉転換
エクソソーム
2 がんの微小環境
1. がん微小環境の概要
2. 上皮性腫瘍細胞と間質細胞との相互作用
3. 腫瘍における血管新生誘導
4. HIF-1 による血管新生因子(VEGF)の発現制御
5. がん細胞における解糖系代謝の亢進
3 がん悪性化とがん幹細胞
1. がん幹細胞の概要
2. 腫瘍におけるクローンの多様化
3. がん幹細胞の薬剤耐性
がん幹細胞マーカー
4 がん特異的シグナル伝達
1. MAPK シグナル
2. PI3K/AKT/mTOR シグナル
3. VEGF シグナル
4. Wnt/β- カテニンシグナル
5. NF-κB シグナル
5章 がんの検査・診断
1 腫瘍マーカー
2 画像診断
1. 単純X 線(レントゲン)
2. X 線コンピュータ断層撮像(X 線CT,CT スキャン)
3. 磁気共鳴画像撮像(MRI 撮像法)
4. 超音波診断法
5. 内視鏡
6. 核医学診断法
3 次世代がん診断(マイクロRNA)
1. リキッドバイオプシーの現状
2. マイクロRNA のバイオマーカーとしての期待
3. エクソソーム中のマイクロRNA による早期がん診断
4. エクソソーム中マイクロRNA によるがん細胞情報の取得
5. 体液中マイクロRNA 診断の今後の展望
早期診断への適応が期待される腫瘍マーカー“PSA”
6章 がん治療と薬物療法の位置付け
1 がん治療の歴史
2 がん治療の基本
1. がん治療の種類
2. がん治療の目的
3. がんの集学的治療
4. 延命・緩和を目的とした治療
5. 臓器横断的な治療
3 手術療法
1. がんの外科学のはじまり
2. がんの手術療法の意義
3. がんの外科手術の高精度化
4. がんに対する移植手術
5. 診断を目的とした外科的処置
6. 姑息的手術
7. がんの予防的手術
4 放射線療法
1. がんの放射線療法のはじまり
2. がんの放射線療法の発展
3. がんの放射線療法の進歩
5 薬物療法
1. 抗がん薬のはじまり
2. 抗がん薬開発の加速
3. 抗がん薬治療の理論
4. 抗がん薬治療の進歩
5. ホルモン剤や分化誘導療法などの新たな治療の登場
6. がん遺伝子に対する分子標的薬の幕開け
7. がん抑制遺伝子の失活を標的とした治療
8. がんの免疫療法
9. がん細胞の薬剤耐性
7章 がん薬物療法における薬効・薬理
1 化学療法(抗がん薬の薬効・薬理)
Ⅰ 化学療法総論
1. 抗がん薬の作用点と分類
2. 抗がん薬に対する耐性
Ⅱ アルキル化薬
1. ナイトロジェンマスタード類(クロロエチルアミン)
2. ニトロソ尿素類
3. スルホン酸エステル類
4. トリアゼン類
5. その他のアルキル化薬
Ⅲ 代謝拮抗薬
1. 葉酸代謝拮抗薬
2. ピリミジン系代謝拮抗薬
3. シトシンアラビノシド系
Ⅳ 抗がん性抗生物質
1. アクチノマイシンD
2. アントラサイクリン系抗生物質
3. マイトマイシンC
4. ブレオマイシン
Ⅴ 天然物由来抗がん薬(抗がん性植物成分薬)
1. 微小管阻害薬
2. トポイソメラーゼ阻害薬
Ⅵ 白金(プラチナ)製剤
1. 構造
2. 作用機序
3. 効能・効果
4. 薬物動態
5. 毒性と副作用
Ⅶ ホルモン剤
1. 男性ホルモンに作用する薬剤
2. 女性ホルモンに作用する薬剤
2 分子標的治療
Ⅰ 分子標的薬総論
1. 抗がん薬と分子標的薬との違い
2. 分子標的薬
3. がんゲノム療法
Ⅱ 抗体薬
1. リガンド標的抗体薬
2. 膜受容体標的抗体薬
3. 膜上分化抗原標的抗体薬
4. 抗体薬物複合体
Ⅲ 低分子薬
1. 非受容体型チロシンキナーゼ標的低分子薬
2. 受容体型チロシンキナーゼ標的低分子薬
3. セリン/ スレオニン標的低分子薬
4. マルチキナーゼ標的低分子薬(マルチキナーゼ阻害薬)
5. キナーゼ標的以外の分子標的薬
Ⅳ がんゲノム医療
1. がんゲノム医療とは
2. がん分子標的薬とプレシジョン・メディシン
3. コンパニオン診断から遺伝子パネル検査へ
4. がんゲノム医療の体制と治療の流れ
5. 行政によるがんゲノム医療の推進
6. がんゲノム医療の今後
3 がん免疫療法
Ⅰ がん免疫療法総論
1. がん細胞に対する免疫監視
2. がん細胞に対する免疫応答
3. がん細胞の免疫系からの回避機構
4. がん免疫療法の分類
Ⅱ がん抗体療法
1. がん抗体療法の概念
2. モノクローナル抗体の開発と分類
3. 抗体医薬品の種類
4. 抗体医薬品の作用機序
5. 抗体医薬品
6. 抗体医薬品の副作用
Ⅲ 免疫チェックポイント阻害薬
1. 免疫チェックポイント阻害薬とは
2. 免疫監視機構とがん免疫療法
3. 免疫逃避機構と免疫チェックポイント分子
4. 免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用
Ⅳ CAR-T 療法
1. CAR-T 療法とは
2. 養子免疫療法
3. キメラ抗原受容体
4. CAR-T 療法
5. TCR 遺伝子改変T 細胞療法
6. CAR-T 療法の副作用と今後の課題
Ⅴ がんワクチン療法
1. がんワクチン研究の歴史
2. がんワクチン療法の種類
3. がんワクチンの現状と将来性
4 がん薬物療法におけるドラッグデリバリーシステム
1. ドラッグデリバリーシステムの役割
2. ドラッグデリバリーシステムと腫瘍微小環境
3. 抗体薬物複合体
4. マイクロカプセル型徐放製剤
5. アルブミンナノ粒子
6. リポソームの腫瘍集積性
7. リポソーム化抗がん薬
8. 臨床応用が期待されるリポソーム
8章 がん薬物併用療法
1 併用の考え方
2 biochemical modulation
1. 5-フルオロウラシル・ロイコボリン併用療法
2. テガフール・ウラシル併用療法
3. テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1 療法)
4. TAS-102(トリフルリジン・チピラシル配合錠)
3 薬物相互作用
1. メルカプトプリンと高尿酸血症治療薬
2. フッ化ピリミジン系抗がん薬(カペシタビン,フルオロウラシル,テガフールなど)とワルファリン
3. フッ化ピリミジン系抗がん薬(カペシタビン,フルオロウラシル,テガフールなど)とフェニトイン
4. テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1)とフルシトシン
5. パクリタキセルとシスプラチン
6. パクリタキセルとドキソルビシン
7. 葉酸代謝拮抗薬(メトトレキサート,ペメトレキセド)と非ステロイド性抗炎症薬
8. イリノテカンとアタザナビル
9. ブレオマイシンとブレンツキシマブ ベドチン
10. CYP3A 系で代謝される抗がん薬
11. 胃酸分泌抑制薬の影響を受ける抗がん薬
4 エビデンスのある併用療法
1. FOLFOX4 療法
2. mFOLFOX6 療法
3. FOLFIRI 療法
4. テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1 療法)
5. 大量メトトレキサート・ロイコボリン救援療法
5 レジメン管理
1. レジメンとは
2. レジメン管理されるようになった経緯
3. レジメンに記載する内容
4. レジメンの申請・審査・登録までの流れ
5. レジメン情報を把握して患者指導に活かす
6. 薬薬連携を見据えたレジメン管理
9章 薬理効果の評価
1 薬物動態(PK/PD)
1. イリノテカン
2. フッ化ピリミジン系抗がん薬
3. 白金(プラチナ)製剤
4. 葉酸代謝拮抗薬の薬物動態
5. 薬物動態に基づいた抗がん薬の血中モニタリング
6. 薬物相互作用
7. 薬物トランスポーターと薬物代謝酵素
2 薬理ゲノム・毒性ゲノム
1. 生殖細胞遺伝子変異
2. 体細胞遺伝子変異
10章 臓器別がん薬物療法と腫瘍随伴症状
1 頭頸部がん
2 脳腫瘍
3 肺がん総論
4 小細胞肺がん
5 非細胞肺がん
6 消化器がん総論
7 食道がん
8 胃がん
9 大腸がん
10 肝細胞がん
11 胆道がん
12 膵がん
13 乳がん
14 子宮がん総論
15 子宮頸がん
16 子宮体がん
17 卵巣がん
18 泌尿器がん総論
19 腎がん
20 前立腺がん
21 膀胱がん
22 造血器がん総論
23 急性白血病
24 慢性骨髄性白血病
25 ホジキンリンパ腫
26 非ホジキンリンパ腫
27 多発性骨髄腫
28 骨軟部腫瘍
29 悪性黒色腫(メラノーマ)
30 腫瘍随伴症状
11章 がん薬物療法の有害事象と支持療法
1 概 要
2 骨髄抑制
3 消化器障害
4 皮膚障害
5 心毒性(心血管障害)
6 神経障害
7 間質性肺障害
8 腎障害
9 インフュージョンリアクション
12章 緩和療法と治療薬
1 緩和医療とは
2 緩和ケアにおける患者の意思確認の重要性
1. インフォームド・コンセント
2. 緩和ケアにおける意思決定
3 がんに伴う疼痛とその治療薬
Ⅰ 痛みの性質・分類とその発症メカニズム
1. 疼痛伝達系
2. 痛みの分類
Ⅱ がん疼痛治療薬の種類と作用メカニズム
1. オピオイド鎮痛薬
2. 麻薬拮抗性鎮痛薬
3. 非オピオイド鎮痛薬
4. 鎮痛補助薬
Ⅲ 痛みの評価尺度
1. 視覚的アナログ評価尺度
2. 数値評価尺度
3. 表情尺度スケール
4. 言語表現評価尺度
Ⅳ WHO 方式がん疼痛治療法
Ⅴ がん疼痛治療薬の類似点・相違点
1. 概要
2. アセトアミノフェンと非ステロイド性抗炎症薬の類似点と相違点
3. オピオイドの類似点・相違点
Ⅵ がん疼痛治療薬の副作用対策
1. オピオイドの副作用対策の重要性
2. オピオイドによる眠気
3. 悪心・嘔吐
4. 便秘
Ⅶ オピオイド鎮痛薬への理解
1. 概要
2. オピオイドへの理解を深める
4 終末期症状とその治療薬
Ⅰ がん終末期に発現する症状と対応
1. 概要
2. 悪液質
3. せん妄
4. その他の症状
Ⅱ がん悪液質の病態生理
1. 概要
2. 症状
3. 発現機序
4. 発症時期
5. リスク因子
Ⅲ がん悪液質の治療
1. 概要
2. 栄養療法
3. 運動療法
4. 薬物療法
5. 心理療法
一般索引
薬剤索引
1 腫瘍の分類
1. 腫瘍の定義
2. 組織発生学的分類:上皮性腫瘍と非上皮性腫瘍
3. 組織型分類:悪性腫瘍の分類
4. 病期分類:TNM 分類と病期分類
2 がん統計の概要
わが国におけるがん死亡と罹患
3 がんの成因
がんのリスク要因
2章 発がん因子と発がん過程
1 化学的因子
1. 多環芳香族炭化水素
2. 芳香族アミノ化合物
3. 有機溶剤
4. 金属
5. 高分子・プラスチックモノマー
6. 高分子添加剤
7. ガス状物質
8. 農薬
9. ダイオキシン類
10. カビ毒(マイコトキシン)
11. ニトロソ化合物
12. 有機フッ素化合物(PFAS)
13. 食用植物
14. 食品添加物
2 生物学的因子
1. 寄生虫
2. 細菌
3. ウイルス
3 物理化学的因子
1. 紫外線
2. 電離放射線
3. 繊維・粒子状物質
4 イニシエーションとプロモーション(多段階発がん)
1. 多段階発がん説
2. プロモーション
3. プログレッション
5 発がん物質の代謝活性化による遺伝子損傷
1. 発がん物質
2. 代謝活性化
3. 代謝活性化された究極発がん物質による遺伝子損傷
6 活性酸素,一酸化窒素による遺伝子損傷
1. 活性酸素種
2. 一酸化窒素
7 遺伝子変異・修復
1. 酵素による直接修復
2. DNA 1 本鎖切断の修復機構
3. DNA 2 本鎖切断の修復機構
4. 損傷乗り越え複製
5. 染色体の異常
8 がん関連遺伝子
がん原遺伝子
9 がんのエピジェネティクス
1. DNA メチル化とは
2. がんにおけるDNA メチル化異常と治療応用
3. ヒストン修飾とは
4. がんにおけるヒストン修飾異常と治療応用
3章 がんの予防
1 一次予防と二次予防
1. がん予防の背景
2. がん予防の分類
3. がん予防の分類と戦略
4. 一次予防の課題と対策
5. 二次予防の課題と対策
2 がんの化学予防物質
3 発がん性リスクアセスメント
1. 発がん性の確認
2. 量- 反応アセスメント
3. 曝露アセスメント
4. リスク判定
4 発がん性物質のスクリーニング法
1. 変異原性試験
2. 染色体異常試験
3. DNA 損傷性試験
4. 遺伝子損傷性のない発がん性物質のスクリーニング法
4章 がんの生物学
1 がんの転移・浸潤
1. 転移のメカニズム
2. 転移と上皮間葉転換
3. 転移の臓器特異性 / 組織向性
上皮間葉転換
エクソソーム
2 がんの微小環境
1. がん微小環境の概要
2. 上皮性腫瘍細胞と間質細胞との相互作用
3. 腫瘍における血管新生誘導
4. HIF-1 による血管新生因子(VEGF)の発現制御
5. がん細胞における解糖系代謝の亢進
3 がん悪性化とがん幹細胞
1. がん幹細胞の概要
2. 腫瘍におけるクローンの多様化
3. がん幹細胞の薬剤耐性
がん幹細胞マーカー
4 がん特異的シグナル伝達
1. MAPK シグナル
2. PI3K/AKT/mTOR シグナル
3. VEGF シグナル
4. Wnt/β- カテニンシグナル
5. NF-κB シグナル
5章 がんの検査・診断
1 腫瘍マーカー
2 画像診断
1. 単純X 線(レントゲン)
2. X 線コンピュータ断層撮像(X 線CT,CT スキャン)
3. 磁気共鳴画像撮像(MRI 撮像法)
4. 超音波診断法
5. 内視鏡
6. 核医学診断法
3 次世代がん診断(マイクロRNA)
1. リキッドバイオプシーの現状
2. マイクロRNA のバイオマーカーとしての期待
3. エクソソーム中のマイクロRNA による早期がん診断
4. エクソソーム中マイクロRNA によるがん細胞情報の取得
5. 体液中マイクロRNA 診断の今後の展望
早期診断への適応が期待される腫瘍マーカー“PSA”
6章 がん治療と薬物療法の位置付け
1 がん治療の歴史
2 がん治療の基本
1. がん治療の種類
2. がん治療の目的
3. がんの集学的治療
4. 延命・緩和を目的とした治療
5. 臓器横断的な治療
3 手術療法
1. がんの外科学のはじまり
2. がんの手術療法の意義
3. がんの外科手術の高精度化
4. がんに対する移植手術
5. 診断を目的とした外科的処置
6. 姑息的手術
7. がんの予防的手術
4 放射線療法
1. がんの放射線療法のはじまり
2. がんの放射線療法の発展
3. がんの放射線療法の進歩
5 薬物療法
1. 抗がん薬のはじまり
2. 抗がん薬開発の加速
3. 抗がん薬治療の理論
4. 抗がん薬治療の進歩
5. ホルモン剤や分化誘導療法などの新たな治療の登場
6. がん遺伝子に対する分子標的薬の幕開け
7. がん抑制遺伝子の失活を標的とした治療
8. がんの免疫療法
9. がん細胞の薬剤耐性
7章 がん薬物療法における薬効・薬理
1 化学療法(抗がん薬の薬効・薬理)
Ⅰ 化学療法総論
1. 抗がん薬の作用点と分類
2. 抗がん薬に対する耐性
Ⅱ アルキル化薬
1. ナイトロジェンマスタード類(クロロエチルアミン)
2. ニトロソ尿素類
3. スルホン酸エステル類
4. トリアゼン類
5. その他のアルキル化薬
Ⅲ 代謝拮抗薬
1. 葉酸代謝拮抗薬
2. ピリミジン系代謝拮抗薬
3. シトシンアラビノシド系
Ⅳ 抗がん性抗生物質
1. アクチノマイシンD
2. アントラサイクリン系抗生物質
3. マイトマイシンC
4. ブレオマイシン
Ⅴ 天然物由来抗がん薬(抗がん性植物成分薬)
1. 微小管阻害薬
2. トポイソメラーゼ阻害薬
Ⅵ 白金(プラチナ)製剤
1. 構造
2. 作用機序
3. 効能・効果
4. 薬物動態
5. 毒性と副作用
Ⅶ ホルモン剤
1. 男性ホルモンに作用する薬剤
2. 女性ホルモンに作用する薬剤
2 分子標的治療
Ⅰ 分子標的薬総論
1. 抗がん薬と分子標的薬との違い
2. 分子標的薬
3. がんゲノム療法
Ⅱ 抗体薬
1. リガンド標的抗体薬
2. 膜受容体標的抗体薬
3. 膜上分化抗原標的抗体薬
4. 抗体薬物複合体
Ⅲ 低分子薬
1. 非受容体型チロシンキナーゼ標的低分子薬
2. 受容体型チロシンキナーゼ標的低分子薬
3. セリン/ スレオニン標的低分子薬
4. マルチキナーゼ標的低分子薬(マルチキナーゼ阻害薬)
5. キナーゼ標的以外の分子標的薬
Ⅳ がんゲノム医療
1. がんゲノム医療とは
2. がん分子標的薬とプレシジョン・メディシン
3. コンパニオン診断から遺伝子パネル検査へ
4. がんゲノム医療の体制と治療の流れ
5. 行政によるがんゲノム医療の推進
6. がんゲノム医療の今後
3 がん免疫療法
Ⅰ がん免疫療法総論
1. がん細胞に対する免疫監視
2. がん細胞に対する免疫応答
3. がん細胞の免疫系からの回避機構
4. がん免疫療法の分類
Ⅱ がん抗体療法
1. がん抗体療法の概念
2. モノクローナル抗体の開発と分類
3. 抗体医薬品の種類
4. 抗体医薬品の作用機序
5. 抗体医薬品
6. 抗体医薬品の副作用
Ⅲ 免疫チェックポイント阻害薬
1. 免疫チェックポイント阻害薬とは
2. 免疫監視機構とがん免疫療法
3. 免疫逃避機構と免疫チェックポイント分子
4. 免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用
Ⅳ CAR-T 療法
1. CAR-T 療法とは
2. 養子免疫療法
3. キメラ抗原受容体
4. CAR-T 療法
5. TCR 遺伝子改変T 細胞療法
6. CAR-T 療法の副作用と今後の課題
Ⅴ がんワクチン療法
1. がんワクチン研究の歴史
2. がんワクチン療法の種類
3. がんワクチンの現状と将来性
4 がん薬物療法におけるドラッグデリバリーシステム
1. ドラッグデリバリーシステムの役割
2. ドラッグデリバリーシステムと腫瘍微小環境
3. 抗体薬物複合体
4. マイクロカプセル型徐放製剤
5. アルブミンナノ粒子
6. リポソームの腫瘍集積性
7. リポソーム化抗がん薬
8. 臨床応用が期待されるリポソーム
8章 がん薬物併用療法
1 併用の考え方
2 biochemical modulation
1. 5-フルオロウラシル・ロイコボリン併用療法
2. テガフール・ウラシル併用療法
3. テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1 療法)
4. TAS-102(トリフルリジン・チピラシル配合錠)
3 薬物相互作用
1. メルカプトプリンと高尿酸血症治療薬
2. フッ化ピリミジン系抗がん薬(カペシタビン,フルオロウラシル,テガフールなど)とワルファリン
3. フッ化ピリミジン系抗がん薬(カペシタビン,フルオロウラシル,テガフールなど)とフェニトイン
4. テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1)とフルシトシン
5. パクリタキセルとシスプラチン
6. パクリタキセルとドキソルビシン
7. 葉酸代謝拮抗薬(メトトレキサート,ペメトレキセド)と非ステロイド性抗炎症薬
8. イリノテカンとアタザナビル
9. ブレオマイシンとブレンツキシマブ ベドチン
10. CYP3A 系で代謝される抗がん薬
11. 胃酸分泌抑制薬の影響を受ける抗がん薬
4 エビデンスのある併用療法
1. FOLFOX4 療法
2. mFOLFOX6 療法
3. FOLFIRI 療法
4. テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤(S-1 療法)
5. 大量メトトレキサート・ロイコボリン救援療法
5 レジメン管理
1. レジメンとは
2. レジメン管理されるようになった経緯
3. レジメンに記載する内容
4. レジメンの申請・審査・登録までの流れ
5. レジメン情報を把握して患者指導に活かす
6. 薬薬連携を見据えたレジメン管理
9章 薬理効果の評価
1 薬物動態(PK/PD)
1. イリノテカン
2. フッ化ピリミジン系抗がん薬
3. 白金(プラチナ)製剤
4. 葉酸代謝拮抗薬の薬物動態
5. 薬物動態に基づいた抗がん薬の血中モニタリング
6. 薬物相互作用
7. 薬物トランスポーターと薬物代謝酵素
2 薬理ゲノム・毒性ゲノム
1. 生殖細胞遺伝子変異
2. 体細胞遺伝子変異
10章 臓器別がん薬物療法と腫瘍随伴症状
1 頭頸部がん
2 脳腫瘍
3 肺がん総論
4 小細胞肺がん
5 非細胞肺がん
6 消化器がん総論
7 食道がん
8 胃がん
9 大腸がん
10 肝細胞がん
11 胆道がん
12 膵がん
13 乳がん
14 子宮がん総論
15 子宮頸がん
16 子宮体がん
17 卵巣がん
18 泌尿器がん総論
19 腎がん
20 前立腺がん
21 膀胱がん
22 造血器がん総論
23 急性白血病
24 慢性骨髄性白血病
25 ホジキンリンパ腫
26 非ホジキンリンパ腫
27 多発性骨髄腫
28 骨軟部腫瘍
29 悪性黒色腫(メラノーマ)
30 腫瘍随伴症状
11章 がん薬物療法の有害事象と支持療法
1 概 要
2 骨髄抑制
3 消化器障害
4 皮膚障害
5 心毒性(心血管障害)
6 神経障害
7 間質性肺障害
8 腎障害
9 インフュージョンリアクション
12章 緩和療法と治療薬
1 緩和医療とは
2 緩和ケアにおける患者の意思確認の重要性
1. インフォームド・コンセント
2. 緩和ケアにおける意思決定
3 がんに伴う疼痛とその治療薬
Ⅰ 痛みの性質・分類とその発症メカニズム
1. 疼痛伝達系
2. 痛みの分類
Ⅱ がん疼痛治療薬の種類と作用メカニズム
1. オピオイド鎮痛薬
2. 麻薬拮抗性鎮痛薬
3. 非オピオイド鎮痛薬
4. 鎮痛補助薬
Ⅲ 痛みの評価尺度
1. 視覚的アナログ評価尺度
2. 数値評価尺度
3. 表情尺度スケール
4. 言語表現評価尺度
Ⅳ WHO 方式がん疼痛治療法
Ⅴ がん疼痛治療薬の類似点・相違点
1. 概要
2. アセトアミノフェンと非ステロイド性抗炎症薬の類似点と相違点
3. オピオイドの類似点・相違点
Ⅵ がん疼痛治療薬の副作用対策
1. オピオイドの副作用対策の重要性
2. オピオイドによる眠気
3. 悪心・嘔吐
4. 便秘
Ⅶ オピオイド鎮痛薬への理解
1. 概要
2. オピオイドへの理解を深める
4 終末期症状とその治療薬
Ⅰ がん終末期に発現する症状と対応
1. 概要
2. 悪液質
3. せん妄
4. その他の症状
Ⅱ がん悪液質の病態生理
1. 概要
2. 症状
3. 発現機序
4. 発症時期
5. リスク因子
Ⅲ がん悪液質の治療
1. 概要
2. 栄養療法
3. 運動療法
4. 薬物療法
5. 心理療法
一般索引
薬剤索引